「なぜこの上司は私の気持ちをわかってくれないんだろう…」そんな思いを抱いたことはありませんか?
職場では、できない人の気持ちがわからない上司に悩まされている方が少なくありません。
上司が何考えてるかわからない状況や、部下の気持ちがわからない上司との関係は、日々のストレスの大きな原因となっています。
特に話が通じないとキレたり、大事なことを言わない上司、さらには守ってくれない上司のもとで働くことは、想像以上に精神的な負担となるものです。
人としておかしい上司だと感じることもあるかもしれませんし、新しい上司への異動で上司が変わるストレスを経験している方も多いでしょう。
この記事では、できない人の気持ちがわからない人の特徴や、部下のメンタルを追い詰めるだめな上司の特徴について解説します。
さらに、ダメな上司だけがする10の発言などを紹介しながら、こうした困難な状況にどう対処すべきかについて、具体的な方法をお伝えします。
仕事の悩みの多くは人間関係、特に上司との関係に起因することが多いものです。
この記事があなたの職場環境改善の一助となれば幸いです。
- 上司が部下の気持ちをわからないのではなく「仕方ない」と判断していることが多い実態
- 「できない人」と思われる根本的な理由と「わかる」と「できる」の違い
- 部下のメンタルを追い詰める上司に共通する特徴と対処法
- 上司との良好な関係を築くための具体的なコミュニケーション方法
できない人の気持ちがわからない上司の本当の姿
上司は本当に部下の気持ちがわからないのか
「上司は部下の気持ちがわからない」というフレーズ、よく耳にしませんか?
実は多くの場合、上司は部下の気持ちを理解していることが少なくないんです。
考えてみてください。ほとんどの上司も最初は部下の立場からスタートしています。
「上の人間は分かっていない」と部下が感じるとき、実際には上司はただ業務の全体像を見据えた判断をしているだけかもしれません。
「部署の責任者をやっていると、日々実感するが、世の中本当にスムーズに行くことなんてまず、ない。何かしらの歪が発生して当たり前なのだ。」
「部下の気持ちが本当に分からない上司なんて、ほぼいない」https://www.orehero.net/entry/2017/12/18/170000
多くの上司は部下が抱える不満や困難を実は理解していて、ただそれを「仕方ない」と判断しているケースが多いのです。
あなたの上司も、実際にはあなたの感じている困難や不満を理解しているかもしれません。
ただ、コミュニケーションスタイルの違いによって、その気持ちが伝わっていないことも多いんですよね。
優れた上司は部下の気持ちに配慮し、「ごめんね」「負担かけるね」といったフォローを入れることで、同じ状況でも部下の受け止め方が大きく変わることを知っています。
問題は「理解していない」ことではなく、「理解しているけれど伝え方が下手」なことかもしれないのです。
上司との関係で悩んでいる場合は、まず「上司は本当に理解していないのか」という視点で考えてみることをおすすめします。
もしかしたら、全体のバランスを取るために苦渋の決断をしている可能性もあるかもしれませんね。
「できない人」と思われる理由とは

あなたは職場で「できない人」と思われた経験はありませんか?
それとも、「なぜあの人はできないのだろう」と思ったことはありませんか?
私たちは往々にして「自分ができること」を基準に他者を判断しがちです。
特に「仕事ができる人」ほど、自分の得意なことが他人にとっても簡単なはずだと無意識に思い込みやすいんです。
「わかっている」ことと「できる」ことは全く別物なのに、多くの上司はこの区別がつかず、部下を責めてしまうことがあります。
「頑張ってるの。ちゃんと勉強もしてるの。でも、できないことをわかってほしい。できない中でも少しずつ善処してるの。だから、できないことを詰めるのではなく、できたことを認めてほしい。」
「クソ上司だった私が初めて知った「できない人」の気持ち」https://note.com/yukij/n/nc2c3e11dbbca
実は私たちは「自分が最初は何もできなかったこと」を忘れていく生き物なんです。
日々の業務に慣れ、スキルが上がっていくうちに、かつての自分が戸惑っていた記憶が薄れていきます。
さらに仕事の適性も大きく関わっています。
あなたにとって簡単なことが、他の人には本当に難しいことかもしれません。
逆に、あなたができなくて悩んでいることが、他の人には簡単なことかもしれないのです。
「できない人」は怠けているわけではなく、本当に「できない」という実感を持っていることが多いです。
そんなとき必要なのは叱責ではなく、できたことを認め、小さな成長を喜ぶ姿勢かもしれませんね。
相手の適性を見極め、その人に合った指導や役割を与えることが、真の「できる上司」の条件なのかもしれません。
部下のメンタルを追い詰めるだめな上司の特徴

部下のメンタルを追い詰めてしまう上司には、いくつかの共通した特徴があります。
これらの特徴に心当たりがあれば、あなたの職場環境は改善の余地があるかもしれませんね。
まず最も大きな特徴は「機嫌の悪さ」です。
「機嫌のよさ」というディープ・スキルを持たない上司は、部下のメンタルを大きく左右してしまいます。
「プライドを持って、仕事をすることは大事なことですが、必要以上に持ちすぎると、人からのアドバイスも素直に聞けなくなり、周りからは扱いにくい存在になってしまうでしょう。」
「人望のある上司」と「ない上司」、顔を見れば一発でわかる決定的な「差」とは?https://diamond.jp/articles/-/330649
上司の「機嫌の悪さ」は部下にとって大きなストレス源となります。
例えば、ミスを報告した際に「不機嫌」な反応を示すだけで、部下は次からミスを隠すようになり、問題が大きくなる前に対処できなくなるんです。
また「感情型上司」も要注意です。
感情がそのまま態度に出てしまい、部下がミスをすると強く叱責したり、嫌なことがあると憮然とした表情をしたりする上司は、部下のメンタルを不安定にさせます。
「ナルシスト型上司」も部下のメンタルを追い詰める傾向があります。
自分がチヤホヤされたい、認められたいという承認欲求が強すぎるあまり、部下の功績を自分のものにしてしまうケースもあるんです。
そして「無関心型上司」も問題です。
部下の気持ちを酌み取るのが苦手で、共感能力が低いタイプは、部下が苦しんでいることに気づかず、サポートができません。
このような上司の下では、部下は「見捨てられた感」を抱き、孤独感からメンタルを病むリスクが高まります。
良い上司は部下の成長を喜び、失敗を成長の機会と捉えます。
そして何より、自分の感情をコントロールし、チーム全体のパフォーマンスを高めることに集中しているものです。
上司が何考えているかわからない時の心理
「あの上司、いったい何を考えているんだろう…」
そんな疑問を抱いたことがある方も多いのではないでしょうか?
上司の言動や決断が理解できず、不安や戸惑いを感じることは誰にでもあるものです。
でも、実は上司が「何を考えているかわからない」と感じるとき、その背景には様々な心理的要因が隠れているんですよ。
まず考えられるのは、上司と部下の間にある「視点の違い」です。
上司は組織全体の目標や経営的な視点から物事を判断していることが多いです。
一方で部下は自分の担当業務や直近のタスクに集中しがちです。
この視点の違いが、上司の考えを「理解できない」と感じさせる大きな原因になっているかもしれません。
もう一つの要因は、コミュニケーションスタイルの違いです。
あなたが詳細な指示を求めているのに対し、上司は大枠だけ示して自主性に任せるスタイルかもしれません。
あるいは、上司自身が「機嫌」を管理できておらず、その日の気分で態度が変わってしまうこともあるでしょう。
「常に機嫌よくいること」が上司として求められる重要なスキルであるにも関わらず、それができていない上司も少なくないんです。
「人望のある上司」と「ない上司」、顔を見れば一発でわかる決定的な「差」とは?https://diamond.jp/articles/-/330649
また、上司が自分の弱みや不安を見せたくないという心理から、本音を隠している場合もあります。
特に中間管理職の上司は、上からのプレッシャーと部下からの期待の間で板挟みになり、本音を出せないこともあるんですよね。
こうした状況を理解することで、「何を考えているかわからない上司」への対応も変わってくるのではないでしょうか。
上司との1on1の機会があれば、組織の方向性や期待について率直に質問してみるのも一つの方法です。
上司の視点を理解することで、あなた自身のストレスも軽減されるかもしれませんよ。
人としておかしい上司の見分け方

「この上司、ちょっとおかしいんじゃないか…」
そんな違和感を抱いたことはありませんか?
職場の上司が「人としておかしい」と感じる瞬間は誰にでもあるものです。
でも、単なる個性なのか、本当に問題があるのか、その見極めは意外と難しいものですよね。
人としておかしい上司には、いくつかの共通した特徴があります。
まず挙げられるのは「一貫性のなさ」です。
機嫌や状況によって態度が極端に変わる上司は要注意です。
特に「感情型上司」は、自分の感情をコントロールできず、部下に八つ当たりすることがあります。
「感情型上司とは、部下がミスをしたりすると「何やっているんだ」と強く叱責したり、嫌なことがあると憮然とした表情をしたり、気持ちがそのまま言動や表情にストレートに出てしまう上司のことを指します。」
部下のメンタル壊す「危険な上司たち」の特徴」https://toyokeizai.net/articles/-/331361?display=b
次に「共感能力の欠如」も重要なサインです。
部下の気持ちや状況を理解しようとせず、自分の基準だけで判断する上司は、人としての基本的な共感能力が不足しているかもしれません。
また「モラルの欠如」も見逃せません。
部下の功績を自分のものにしたり、ミスを部下に押し付けたりする上司は、基本的なモラルに問題があると言えるでしょう。
「人としておかしい上司」の最も危険な特徴は「パワーハラスメント」の傾向です。
威圧的な態度や過度な叱責、理不尽な要求などは、単なる「おかしさ」を超えて、ハラスメントに該当する可能性があります。
しかし、注意したいのは「単に合わない」だけの場合もあるということです。
価値観や仕事の進め方が合わないだけで、必ずしも「人としておかしい」わけではないこともあるんです。
こうした上司との付き合い方は、距離を置きつつも最低限のコミュニケーションを保つことが大切です。
あなた自身のメンタルを守りながら、職場環境を改善する方法を模索していきましょう。
できない人の気持ちがわからない上司への対応法
ダメな上司だけがする10の発言とは
上司の何気ない一言が、私たちの仕事へのモチベーションを大きく左右することがありますよね。
特に「ダメな上司」と呼ばれる人たちには、共通する発言パターンがあるんです。
まず1つ目は「お前は向いていない」という発言です。
適性は確かに大切ですが、成長の機会を奪うような言い方は問題です。
「お前、向いてないよ」と言われたことがある。その時は、わかってはいるけどそこまで言うか…と思った。だけど、仕事の向き不向きで本人だけでなく、周りもフォローやサポートの負担が増える以上、向いてない人に向いてないと教えてあげるのは優しさだったのだなと、今では思う。」
「できる人にはできない人の気持ちがわからないって話」https://note.com/uesugitakako/n/n31e8741ebebe
2つ目は「なぜできないの?」という問いかけです。
これは一見合理的に聞こえますが、「わかっているのにできない」という状況を理解していない証拠かもしれません。
3つ目は「俺の若い頃は…」という過去の自分と比較する発言です。
時代も状況も異なる中で、単純比較は無意味ですよね。
4つ目は「言わなくてもわかるだろ」という暗黙の了解を求める言葉です。
これは典型的な「できない人の気持ちがわからない上司」の発言です。
5つ目は「それくらい自分で考えろ」という丸投げの言葉です。
育成という視点が完全に欠けています。
6つ目は「忙しいんだ、後にしてくれ」と常に部下を後回しにする発言です。
7つ目は「お前のせいで」と責任転嫁する言葉です。
8つ目は「誰でもできる仕事だ」と部下の仕事を軽視する発言です。
9つ目は「私の言うとおりにやれ」と思考停止を強いる言葉です。
そして10個目は「他の人はできているのに」という比較による叱責です。
こうした発言をする上司は、部下の成長よりも自分の権威や立場を優先している可能性があります。
あなたの上司がこうした発言をしていたら、それは単なる個性ではなく、上司としての資質に問題があるかもしれません。
優れた上司は「わかっているけどできない」という状況を理解し、一人ひとりの適性や成長段階に合わせたサポートをします。
ただ、こうした認識は上司自身が気づきにくいものでもあります。
建設的なフィードバックを伝える機会をが持てたならよいのですが、なかなかそんな機会はないですよね。でもこれらのことを知っておくだけで上司を客観的にみることができるようになるので、理解する手助けになります。
自分がそんな上司にならないというリストにもなりますね。
上司が話を聞いてくれずキレた時の対処法

上司が突然キレてしまった…
そんな経験は誰にでもあるのではないでしょうか?
特に「話を聞いてくれない上司」がキレると、状況はさらに複雑になりますよね。
まず大切なのは、こうした状況でも冷静さを保つことです。
上司がキレている時、その場で反論や弁解をすると、火に油を注ぐ結果になりかねません。
「感情型上司」の場合、まずはその怒りの感情が落ち着くまで待つことが賢明です。
「こんな上司は、日頃からちょっとした雑談などで楽しそうな雰囲気をつくることが大切です。ミスをしたときに延々と言い訳をするのではなく、単刀直入に謝ると、思いのほか、うまくいくことが多いです。」
感情が高ぶっている時は、相手の言葉を理解する余裕がないものです。
そんな時は、まず謝罪し、「後ほど改めてお時間をいただけませんか?」と切り出すのが効果的です。
時間を置くことで、お互いの感情が落ち着き、建設的な会話ができるようになります。
次に重要なのは、コミュニケーションの方法を工夫することです。
話を聞いてくれない上司には、口頭だけでなく、メールや資料など「目に見える形」での情報提供が効果的なことがあります。
また、上司のタイプによって対応を変えることも大切です。
「ナルシスト型上司」なら、上司の意見を尊重する姿勢を見せながら自分の考えを伝えるといいでしょう。
「自分が認められたいという承認欲が強いので、相手の存在感を認めることが大切です。合わないと思っても、上司の言うことに耳を傾け、尊重する姿勢を見せるのがいい対策法です。」
「無関心型上司」には、明確かつ簡潔に要点を伝えることが大切です。
彼らは共感することが苦手なので、感情面ではなく事実や数字で語りかけると効果的です。
そして最も重要なのは、自分自身のメンタルを守ることです。
上司の怒りは、必ずしもあなた個人に向けられたものではないかもしれません。
上司自身のストレスや、あなたが知らない他の要因が影響している可能性もあります。
あなた自身の心の健康を守るために、信頼できる同僚や友人に話を聞いてもらったり、ストレス発散の時間を持つことも大切ですよ。
大事なことを言わない上司との付き合い方

「もっと早く教えてくれればよかったのに…」
大事な情報をタイミングよく共有してくれない上司との仕事は、本当に難しいものですよね。
でも、こうした状況でも上手く対応する方法はあるんですよ。
まず、なぜ上司が大事なことを言わないのか、その理由を考えてみましょう。
多くの場合、悪意があるわけではなく、「言った」と思い込んでいたり、「言わなくても分かるだろう」と考えていたりするのかもしれません。
「無関心型上司」の特徴として、部下の気持ちを酌み取るのが苦手という点があります。
「このタイプの上司は、あなたの気持ちをわかっていないことが問題です。
はっきり言わないとわかってもらえないと知っておきましょう。遠慮せずに、上司にははっきりと伝えることが大切になってきます。」
こうした上司と付き合う第一の方法は、積極的に質問することです。
曖昧な指示や情報があれば、「確認させてください」と丁寧に聞き返してみましょう。
メモを取りながら「〇〇という理解で合っていますか?」と確認すれば、認識のズレを防げます。
第二に、定期的な報告やミーティングの習慣を作ることです。
週に一度でも定期的なコミュニケーションの機会があれば、必要な情報が共有される可能性が高まります。
第三に、プロジェクト単位での「見える化」を心がけることも有効です。
タスク管理ツールやプロジェクト管理シートを活用し、進捗状況や課題を可視化しておけば、上司も状況を把握しやすくなります。
第四に、同僚との情報共有ネットワークを構築しておくことも大切です。
上司から直接情報が得られない場合でも、同僚から必要な情報を収集できることがあります。
そして最後に、上司のコミュニケーションスタイルを理解し適応することです。
「優等生型上司」なら、彼らの出世意欲や上層部への配慮を理解した上で接すると、より多くの情報が得られるかもしれません。
大事なことを言わない上司との関係は簡単ではありませんが、こうした工夫を重ねることで、徐々に状況は改善していくものです。
あなた自身がプロアクティブな姿勢を持ち続けることが、この状況を乗り越える鍵となりますよ。
上司が守ってくれない時の自己防衛術
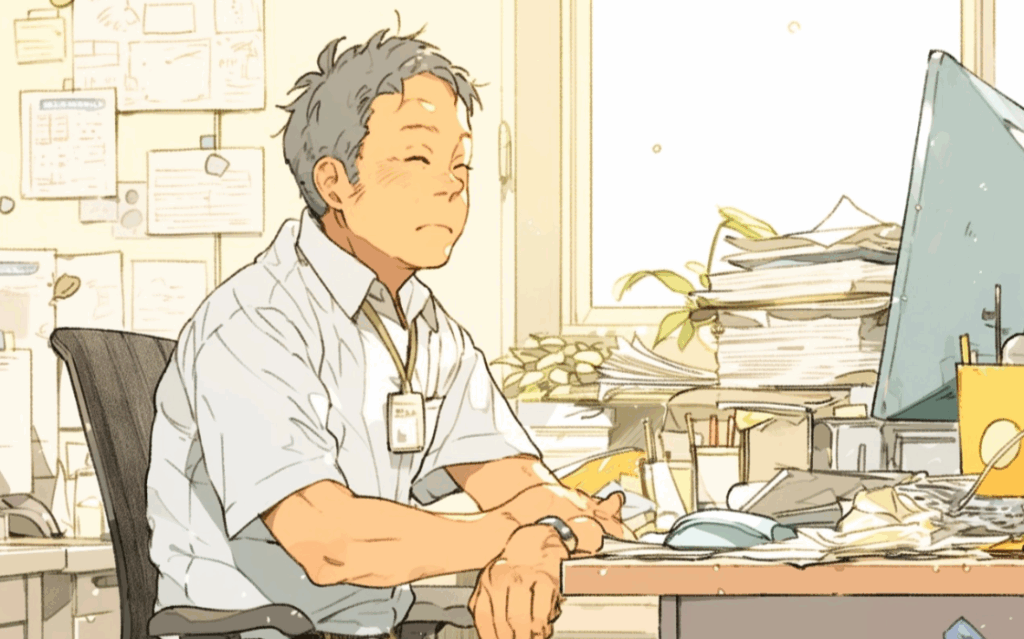
理想的には、上司は部下を守り、サポートする存在であるべきですが、残念ながら現実はそうでないことも多いんです。
まず大切なのは、こうした状況を冷静に受け止めることです。
上司が守ってくれない理由はさまざまで、単に「無関心型上司」だったり、自分自身が精一杯で余裕がなかったりする場合もあります。
この状況で最も重要なのは、自分自身を守るための「自己防衛術」を身につけることです。
まず第一に、すべてを記録に残す習慣を持つことをおすすめします。
重要な指示や決定事項は、メールやチャットで確認し、口頭のやり取りでも後からメールで「〇〇という認識で合っていますか?」と確認するといいですよ。
これによって、後から「言った・言わない」の議論を避けることができます。
第二に、「見える化」を徹底することです。
プロジェクトの進捗状況や問題点を可視化し、チーム全体で共有することで、問題が発生した際の責任の所在を明確にできます。
例えば週報やタスク管理ツールを活用して、自分の仕事の状況を常に「見える」状態にしておくといいでしょう。
第三に、同僚や他部署との良好な関係を構築しておくことも大切です。
上司以外にも自分の仕事を理解し、評価してくれる人がいれば、いざという時の助けになります。
第四に、自分のスキルと成果を客観的に示せるようにしておくことです。
定量的な成果や、受けた評価を記録しておけば、自分の市場価値を示す際に役立ちます。
第五に、必要な場合は上司の上司やHRに相談することも選択肢として持っておきましょう。
ただし、これは最終手段として考え、まずは直接の上司との関係改善を試みることが大切です。
そして何より、心身の健康を守ることを最優先にしてください。
上司が守ってくれない状況は精神的に大きな負担となります。
定期的な休息や趣味の時間を確保し、ストレスを溜め込まないようにすることが重要です。
状況によっては、転職を視野に入れることも選択肢の一つです。
自己防衛は大切ですが、長期的に見て自分の成長や幸福を最優先に考えることを忘れないでくださいね。
上司との関係が変わるストレスへの対策

「昨日までの良好な関係が、今日突然変わってしまった…」
上司との関係性が変化することは、私たちに大きなストレスをもたらします。
特に、新しい上司に変わったときや、これまで良好だった関係が突然冷え込んだときなど、その変化への適応は容易ではありませんよね。
まず理解しておきたいのは、上司との関係変化は誰にでも起こりうることです。
組織改編や人事異動、あるいは上司自身の置かれた状況の変化によって、これまでの関係性が一変することはよくあります。
この変化に対処するための第一歩は、状況を冷静に観察することです。
上司の言動や態度の変化に敏感になり、どのような対応が求められているのかを見極めることが大切です。
次に、コミュニケーションの取り方を見直してみましょう。
新しい上司の場合、コミュニケーションスタイルや期待することが前任者と異なることが多いものです。
例えば、前の上司が細かい報告を求めていたのに対し、新しい上司は大枠だけを把握したいというケースもあります。
また、上司のタイプに応じた対応を心がけることも効果的です。
例えば「ナルシスト型上司」なら、彼らの貢献を認め、適切な敬意を示すことで関係が円滑になることがあります。
「感情型上司」なら、彼らの感情の起伏を理解し、良い機嫌の時にコミュニケーションを取るといいでしょう。
ストレスを管理するための時間とエネルギーを確保することも重要です。
運動や趣味、友人との時間など、仕事から離れてリフレッシュする機会を定期的に持ちましょう。
また、同僚や友人との対話を通じて、感情を吐き出す機会を持つことも効果的です。
ただし、職場での愚痴や噂話は避け、建設的な対話を心がけることが大切ですよ。
そして最も重要なのは、自分自身の成長に焦点を当てることです。
上司との関係変化をキャリアの学びの機会と捉え、様々なタイプの上司に対応できる柔軟性を身につけることで、長期的には大きな財産となります。
上司との関係が変わるストレスは避けられないものですが、それにどう対応するかがあなたの成長を左右します。
この経験を通じて、より強く、柔軟なビジネスパーソンへと成長していくきっかけにしてみませんか?
あなたができる職場環境の改善方法
実は、職場環境の改善は、トップダウンだけでなく、一人ひとりの小さな行動から始まるものなんです。
まず認識したいのは、職場環境は複雑なエコシステムだということ。
上司、同僚、部下、そして自分自身の関係性やコミュニケーションが、職場の雰囲気を形作っています。
そして、あなた自身ができる改善にはさまざまな方法があるんですよ。
第一に、ポジティブなコミュニケーションを意識的に増やしてみましょう。
例えば、同僚の成果を認め、感謝の言葉を伝えるといった小さな行動が、職場の空気を大きく変えることがあります。
第二に、建設的なフィードバック文化を育むことです。
問題点を指摘するだけでなく、具体的な改善案を提案する習慣を身につけると、より前向きな議論が生まれやすくなります。
第三に、チームワークを促進する小さな習慣を取り入れることです。
例えば、定期的なランチ会や、短時間のチームビルディング活動を提案してみるのはいかがでしょうか。
こうした非公式な交流が、チームの結束力を高めることにつながります。
第四に、自分自身の「できない人の気持ち」への理解を深めることです。
誰しも得意不得意があり、あなたにとって簡単なことが、他の人にとっては難しいこともあるんですよね。
第五に、1on1ミーティングの文化を広めることも効果的です。
上司と部下、あるいは同僚同士で、定期的に1対1で対話する機会を持つことで、普段言いづらい課題や改善点を話し合える場が生まれます。
もちろん、あなた一人の力では変えられないことも多いでしょう。
でも、「小さな成功体験」を積み重ねることが大切です。
すべてを一度に変えようとするのではなく、できることから少しずつ始めていきましょう。
最後に、自分自身が「理想の同僚」「理想の上司」になることを意識してみてください。
チームメンバーそれぞれの強みを活かし、弱みをサポートする文化は、あなた自身の行動から始まるものです。
職場環境の改善は一朝一夕にはいきませんが、あなたの小さな行動が、やがて大きな変化を生み出す第一歩となるかもしれません。
勇気を持って、今日からできることから始めてみませんか?
できない人の気持ちがわからない上司の対処法と改善ポイント
記事の内容のポイントを以下のようにまとめました。
- 多くの上司は部下の気持ちを理解しているが「仕方ない」と判断している
- 「わかっている」と「できる」は別物であることを認識すべき
- 「機嫌の悪さ」は部下のメンタルを著しく損なう
- 上司と部下では物事を見る視点や立場が根本的に異なる
- 感情型上司は気分をそのまま態度に出してしまう
- 無関心型上司には要点を明確に伝える必要がある
- ナルシスト型上司は存在感を認めるアプローチが効果的
- 「言わなくてもわかるだろ」は典型的なダメ上司の発言
- 上司がキレた時は時間を置いて冷静になってから話し合う
- 大事なことを言わない上司には積極的に質問し確認する
- 上司が守ってくれない場合は全てを記録に残す自己防衛が必要
- 新しい上司との関係構築には相手のスタイルを観察し適応する
- 適性に合った役割を与えることが真の「できる上司」の条件
- 職場環境の改善は個人の小さな行動から始まる
- チーム内の心理的安全性が職場のパフォーマンスを高める


