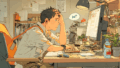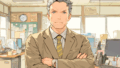パートナーとの話し合いで「黙られる」経験はありませんか?
大切な話をしようとすると、相手が突然無言になったり、その場から逃げ出したりして、結局何も解決しないというパターンに悩んでいる方は少なくありません。
特に男女間では、コミュニケーションの目的そのものが異なることが多く、「話し合い」という同じ言葉を使っていても、まったく違うことを期待していることがあります。
女性は「共感思考」、男性は「課題解決思考」を持つ傾向があり、このギャップが話し合いの障壁になっているのかもしれません。
この記事では、話し合いができずに黙ってしまう相手の心理パターンや、タイプ別の特徴、そして効果的なコミュニケーション方法について解説します。
「逃げる・ごまかす」「黙り込む」「キレる・怒り出す」といった異なるタイプの相手との向き合い方や、情動的共感と認知的共感の使い分け方など、実践的なアドバイスを紹介していきます。
自分自身が黙るタイプだという方のための改善策や、話し合いの目標設定を見直す方法も含め、より良い関係づくりのヒントを見つけてください。
- 男女間の思考パターンの違い(共感思考と課題解決思考)が話し合いに与える影響
- 話し合いで黙る人の心理的背景や8つの心理パターン
- 黙るタイプ別(逃げる・ごまかす、黙り込む、キレる・怒り出す)の特徴と対処法
- 話し合いを円滑にするためのコミュニケーション技術や場・時間の選び方
話し合いができない男性が黙る心理と特徴
男女の共感思考と課題解決思考の違い
話し合いの場で男女がすれ違いを感じることは、珍しくないことだと思います。
こうした「話し合いができない」と感じる瞬間には、実は男女間の思考パターンの違いが大きく影響しているんです。
私たちの多くが経験していることですが、女性は「共感思考」を持つ人が多く、男性は「課題解決思考」を持つ傾向があるんですね。
例えば、「皿を洗え」という指示に対して、女性は「やれ」と言われると不快に感じることが多いんです。
これは「言い方」に敏感だから。
一方で男性は、言い方より内容自体に焦点を当て、納得できればやるし、納得できなければどんな言い方でもやらない傾向があります。
女性が求める「話し合い」とは「私の感情に私と同じくらいの気持ちで向き合ってほしい」という願いであることが多いのです。
対して男性が考える「話し合い」は「課題解決に向かっていく論理的な話」を意味することが多いんですね。
この違いを理解していないと、同じ「話し合い」という言葉を使っていても、まったく異なることを期待してしまいます。
恋愛心理学では、こうした違いの背景には昔の生活様式が影響しているという説もあります。
男性は家族を養うために食料を集める役割、女性は子育てや地域での人間関係を円滑にする役割があり、そうした役割分担が現代にも名残を残しているという考え方です。
個人差はもちろんありますが、こうした傾向を知っておくことで、パートナーの言動の理解が深まるかもしれませんね。
実際のコミュニケーションでは、女性側が「要望を具体的に伝える」努力をすることで、男性側の理解が進むことも多いようです。
「言い方が嫌」という抽象的な表現ではなく、「語尾はこうしてほしい」「このタイミングでこういう発言はやめてほしい」といった具体的な指示の方が、男性にとっては理解しやすいのです。
一方で男性側も、「結論をせかさない」「オチを求めすぎない」という姿勢を心がけることで、コミュニケーションがスムーズになることがあります。
共感にも「情動的共感」と「認知的共感」の2種類があることを知っておくと良いでしょう。
情動的共感は「心から同じ気持ちになって一緒に泣いてあげる」というもので、認知的共感は「状況を把握した上で『あなたはそう感じるんだね』と相手を理解する」というものです。
お互いの思考パターンの違いを理解し、歩み寄る姿勢を持つことが、より良い関係づくりの第一歩になると言えるでしょう。
話し合いができない男性タイプ①:逃げる・ごまかす
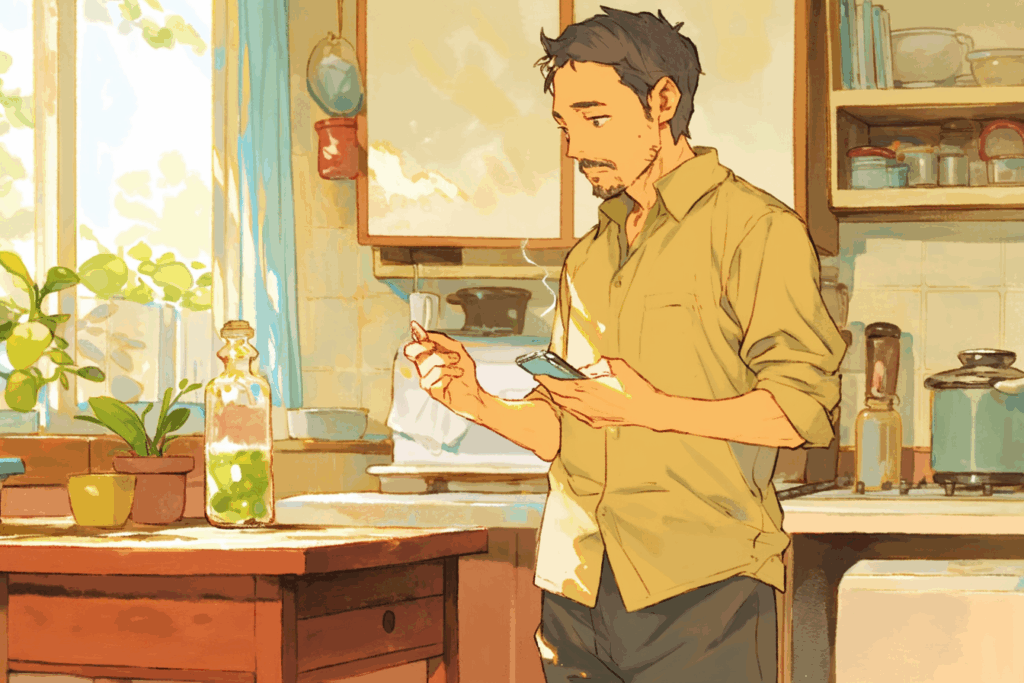
パートナーとの話し合いで、そもそも会話の場を持つことさえ難しいと感じることはありませんか?
これは「逃げる・ごまかす」タイプの特徴的な行動パターンなんです。
このタイプの人は、話し合いが始まりそうになると「うーん」と曖昧な返事をしたり、トイレやお風呂に逃げてしまったりします。
時には話を聞いているように見せかけながら、テレビやスマホをいじって実際は集中していないこともあるんですね。
なぜこのような行動を取るのか、いくつかの心理が考えられます。
まず一つ目は、仕事や日常生活で疲れていて、家でまで頭を使いたくないという気持ちがあるのかもしれません。
「やっと家で休める」と思ったタイミングで、責任の伴うような問題について話し合わなければならないとなると、つい逃げたくなるのかもしれないんです。
二つ目は、話し合うことで自分に不利な結果になることが予想されるから、という理由も。
例えば家事の分担について話し合うとなれば、自分の負担が増えることが予想できるため、話し合いを避けようとする場合もあります。
また、女性の話し方が理解できないことも原因の一つかもしれません。
女性は「会話しながら相手の返事や反応も見て最終的な考えをまとめる」という話の進め方をする人が多いと言われています。
しかし男性からすると、最終的に何を話し合いたいのかが分からないまま長い話を聞かされることになり、集中力が途切れてしまうこともあるようです。
さらに、「考えとくわ」と言って先延ばしにしているうちに、相手がうまくやってくれるだろうと他力本願になるケースもあります。
こうしたタイプの男性に対しては、話し合いの前にその時間と場所をはっきり伝えることが効果的です。
「今、15分くらい話せる?」と聞いてみて、反応が悪ければ「週末でもいいけどどう?」と予約しておくと良いでしょう。
また話し合いの最初に、「今日はこの話なんだけど」とテーマをはっきりさせることがポイントです。
また、伝達手段や場所を変えてみることも有効かもしれません。
スマホのメッセージアプリやメールなど、文字でのコミュニケーションであれば、感情的にならずに本題だけを伝えることができる場合もあります。
自宅ではなく、外出先のカフェなど落ち着いた場所での話し合いも検討してみましょう。
相手が逃げるタイプだと分かったら、それを責めるのではなく、どうすれば話し合いやすい環境になるかを考えてみることが大切ですね。
話し合いができない男性タイプ②:黙り込む
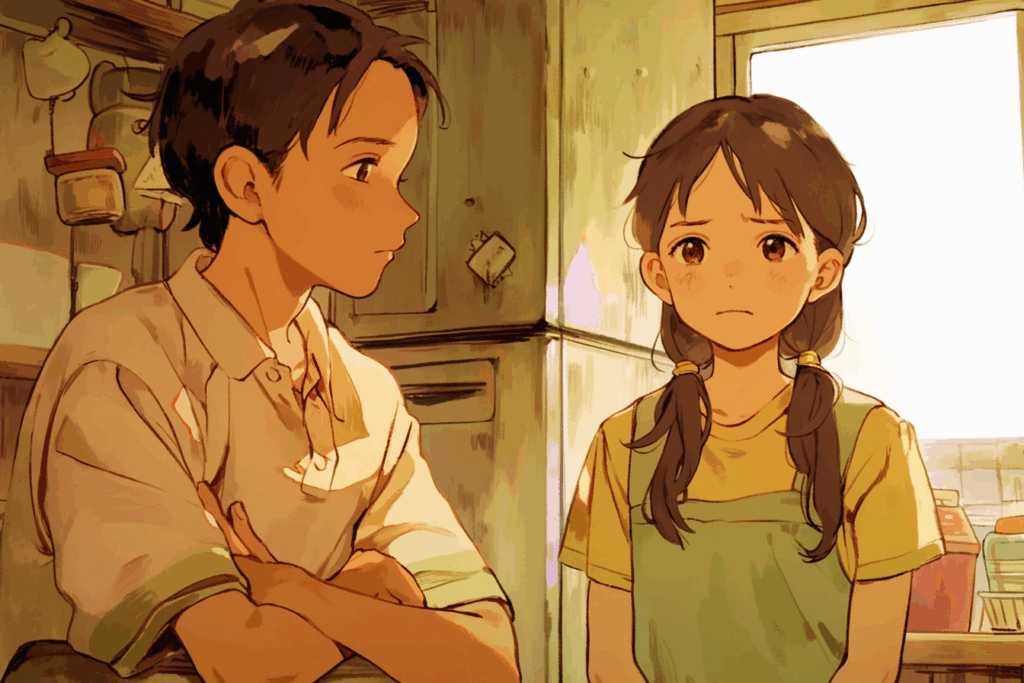
問題が起きたとき、あるいは意見の食い違いがあったとき、パートナーが急に黙り込んでしまうことはありませんか?
これは比較的穏やかな性格の男性に多いタイプで、「黙り込むタイプ」と言われています。
このタイプの人は話し合いには応じてくれるものの、途中で黙り込んでしまい、結局何も決まらないという状況になりがちです。
黙り込むタイプの多くは、口論やケンカが苦手な人が多いんです。
温和な性格で、一緒にいると安心感があるタイプですが、反面、嫌なことを嫌と言えない、人とぶつかるのが怖いという弱みを持っていることがあります。
では、なぜ黙り込んでしまうのでしょうか?
まず一つ目の理由として、口下手でうまく表現できない、あるいは考えをまとめるのに時間がかかるということが挙げられます。
世の中には答えをパッと出せる回転の早い人もいれば、納得するまでじっくり考えてからでないと答えを出せない熟考型の人もいます。
これはどちらが優れているということではなく、その人の個性なんですね。
熟考タイプの人が、相手の「どう思う?」という問いに対し、適当に返事はしたくないけれど、すぐには答えられないという状況で黙り込むことがあります。
二つ目の理由として、何か言っても否定されたり丸め込まれたりするという経験から、話すこと自体をあきらめている場合もあります。
「俺はこう思うけど…」と言いかけても、いつも「でもね、そうするとこうなるじゃない?だからやめたほうがいいと思うの」と遮られてしまうので、話し合いをあきらめてしまっている男性もいるようです。
三つ目の理由として、自分の気持ちに鈍感であるケースもあります。
小さい時から自分の気持ちを伝えてこなかったり、自分の本当の気持ちを後回しにしてきたりすると、「嫌だ」「イライラ」などの感情は感じるものの、「具体的に何が嫌だったのか」がすぐには分からず、伝えられないことがあるんです。
このようなタイプのパートナーとどう向き合えばいいのでしょうか?
まずは相手のペースに合わせることが大切です。
話すスピードやリズムを相手に合わせ、ゆっくり聞き出す姿勢を持ちましょう。
「ゆっくりでいいから意見を教えて?」「待っているから聞かせてほしい」などと時間をかけて聞くことが効果的です。
そして、自分が感情的にならないことも重要です。
怒ったり泣いたりと感情を高ぶらせすぎると、黙るタイプの人はますます話せなくなってしまいます。
安心して話せる環境を作り、「素直な気持ちを話してくれても、あなたを嫌いになったり怒ったりしない」ということを伝えることで、少しずつ心を開いてくれるかもしれませんね。
黙り込むタイプの人との関係では、忍耐強さと相手への理解が特に必要となります。すぐに変化は見られないかもしれませんが、長い目で見ることが大切だと思います。
話し合いができない男性タイプ③:キレる・怒り出す
パートナーと大切な話し合いをしようとしたとき、相手が突然感情的になったり、キレてしまったりすることはありませんか?
私たちが「話し合いができない」と感じる三つ目のタイプが、「キレる・怒り出す」パターンなんです。
このタイプの男性は、困っていることや検討事項を話し合おうとすると、すぐに感情的になり、建設的な会話が成立しないことが特徴です。
なぜこのような反応になってしまうのか、いくつかの心理的背景があります。
まず一つ目は、「自分の考えだけが正しい」と思い込んでいる場合です。
誰でも自分が間違っていると思う行動はしないものですが、このタイプの人は特に「自分は正しいのだから、間違っているのは相手のほう」という思い込みが強い傾向があります。
そのため、自分と異なる意見を持つ相手に対して腹を立ててしまうのです。
「自分は正しいのだから、間違っているのは妻のほう。当然妻が折れるべき」
引用元記事:「話し合いできない夫のタイプ③キレる・怒り出す」
二つ目は、複雑な問題を考えることにストレスを感じ、イライラしてしまう場合です。
子育ての問題や親の介護など、様々な要素が絡み合う課題については、多角的に考え、異なる視点から検討する必要があります。
しかし、自分以外の人の気持ちや自分の決断が与える影響などを想像するのが苦手な人は、考えがまとまらずにイライラし、「もう知らん!」と怒り出してしまうことがあるんです。
三つ目は、「人格を否定された」と誤解してしまうケースです。
服を脱ぎっぱなしにする、子供に乱暴な言葉遣いをするといった「行為」に対して注意をしても、それを「自分という人間への否定」と捉えてしまう人がいます。
妻としては特定の行動について話し合いたいと思っているのに、夫の側は自分の人格全体を否定されたと感じてしまい、怒りの感情が生まれるのです。
そして四つ目は、そもそも話し合いではなく「同意の強制」「ダメ出し」「謝罪要求」「ケンカを売る」といった別の目的があると感じている場合です。
パートナーが「話し合おう」と言っていても、実際には自分の意見を通すことが目的だと感じると、男性は防衛的になり、怒りで反応してしまうことがあります。
このようなタイプのパートナーとどう向き合えばいいのでしょうか?
まず大切なのは、本当に「話し合い」をしたいのか、それとも別の目的があるのかを自分自身で見つめ直すことかもしれません。
もし本当に相手の考えを知り、どうしたらいちばんいいのかを一緒に考えたいのであれば、「これはお願いなんだけど…」「いつもありがとう、でも1つだけどうしても気になるから聞いてくれる?」といった言葉で切り出すと、相手も防衛的になりにくいでしょう。
また、話し合いの場を設定する際は、相手の状態に配慮することも重要です。
仕事で疲れて帰ってきた直後や、イライラしている様子が見えるときは避け、お互いがリラックスできるタイミングを選びましょう。
場合によっては、自宅ではなくカフェなど外出先での方が、落ち着いて話せることもあります。
キレやすいタイプの相手との話し合いでは、明確なゴール設定も助けになります。
「今日はとりあえず相手の気持ちを聞くところまでにしよう」など、一度に全てを解決しようとせず、小さなステップに分けて進めていくことで、お互いのストレスも軽減できるかもしれませんね。
パートナーとの関係は長い時間をかけて築いていくもの。一朝一夕に変わることは難しいかもしれませんが、少しずつ理解を深め、コミュニケーションの方法を工夫していくことで、より良い関係を築いていくことができると思います。
黙り込む男性の8つの心理パターン

話し合いの場で黙り込んでしまう男性を前にして、「どうして何も言ってくれないの?」と思ったことはありませんか?
相手に黙られることで、私たちは不安を感じたり怒りが増したりしてしまうものですが、黙る側にも様々な思いがあるのです。
黙り込む男性の心の中では、実はどのようなことが起きているのでしょうか。その心理パターンを理解することで、より良いコミュニケーションへの糸口が見つかるかもしれません。
まず一つ目の心理は、「嫌われたくない」という思いからです。
相手に傷つくことや怒らせることを言って嫌われてしまうことを恐れている人は、黙ることを選びます。
他人からの目をとても気にし、自分に自信がない人に多いパターンです。
二つ目は、「こらえている」状態です。
相手へ指摘や反論などしたい気持ちを必死にこらえている人もいます。
自分がいら立っていて、今言葉を発したら相手をますます怒らせてしまうかもしれないと考え、黙って堪えているのです。
このタイプの人は、言葉は発しないものの、表情や仕草に感情が表れていることが多いですね。
「プライドが高く負けず嫌いな性格ですが、忍耐強さも持っています。このタイプの人は、言葉は発しないものの、大概表情や仕草に感情が表れています。」
引用元記事:「「黙る人」に共通する「8つの心理」とは」
三つ目は、「傷つけたくない」という優しさからです。
余計なことを言って相手を傷つけないようにするために黙る選択をしている人もいます。
相手のことを思いやる気持ちを忘れずに持つことのできる優しい性格の人ですが、あまりに気を回しすぎて自分のことは後回しになりがちな面もあります。
四つ目は、「怒らせたくない」という心理です。
不機嫌だったり興奮していたりする相手をこれ以上感情的にさせたくないと思って黙る人もいます。
冷静で合理的な判断のできる人ですが、平和主義、事なかれ主義的なところもあり、問題を先延ばしにしたり逃げたりすることも多いでしょう。
五つ目は、「あきらめている」状態です。
「この相手には何を言っても無駄だ」「説明したところでわかってもらえないだろう」と、話し合うことをあきらめている人もいます。
過去の経験から、会話しても意味がないと思っているため、自分からは何も発信しようとしないのです。
六つ目は、「自分を責めている」心理です。
自分のした言動に対して後悔や反省をしているため、黙っている場合もあります。
自分が悪いと思っていて、反論や弁明をしようと思わないので、黙って相手の話を聞くことに徹しようと考えています。
七つ目は、「理解できていない」状態です。
相手がなぜそのような言動に至っているのかが理解できていないため、黙る人もいます。
相手の話や出来事を理解していないので黙るしかない、または理解していないことを悟られないようにするために黙っています。
八つ目は、「上手く表現できない」というもどかしさからです。
自分の気持ちを表現するのが苦手なので、つい黙ってしまう人もいます。
喜怒哀楽をストレートに出すことに抵抗があったり、表現の仕方がわからなかったりする不器用な人に多いパターンです。
このように、黙り込む理由は一つではなく、その人の性格や育った環境、過去の経験など様々な要因が影響しています。
なかでも小さい頃に自分の意見を言えず押さえつけられたり、意見を言ってもいつも否定されたりした経験がある人は、大人になっても自分の気持ちを表現することに恐れを感じることがあるのです。
黙り込む相手とのコミュニケーションでは、まず相手のペースに合わせることが大切です。
早口で話したり、間髪入れずに話し続けたりするのではなく、相手が考える時間を持てるようなゆとりを持ちましょう。また、感情的にならず、安心して話せる環境を作ることも重要です。
「相手のペースに合わせる」「ゆっくり聞き出す」「感情的にならない」「大丈夫だと伝える」
引用元記事:「「黙る人」と上手に関わるにはどうすれば良い!?」
時には「考える時間もらってもいい?」と伝えることを相手に促すのも一つの方法です。
黙り込んでしまう相手に対して「なんで黙っているのか?」が分からないと、こちらも不安になりますよね。
「考えている」のか「もう話したくない」のか「放棄した」のかが分かれば、次の対応もしやすくなります。
お互いの対話がうまくいかないとき、つい相手のことばかり責めてしまいがちですが、自分自身のコミュニケーションスタイルを振り返ることも大切です。
相手との関係をより良くしたいと思うのであれば、まずは相手の「黙る」という行動の背景にある心理を理解し、そこから歩み寄りの一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
話し合いができず黙る相手との上手な付き合い方
相手のコミュニケーションスタイルを理解する
パートナーとの会話がうまくいかないとき、「なぜ分かり合えないんだろう」と悩んだことはありませんか?
実は、この悩みの根本には、お互いのコミュニケーションスタイルの違いが隠れていることが多いんです。
男女の間ではとくに、コミュニケーションの目的そのものが異なることがよくあります。
女性は「共感思考」の人が多く、男性は「課題解決思考」の人が多いという傾向があるんですね。
私たちが話し合いで目指すものが、そもそも違うところからスタートしているんです。
例えば、女性のいう「話し合いにならない」とは、「私の感情に私と同じくらいの気持ちで向き合ってくれない」という不満であることが多いです。
一方、男性のいう「話し合いにならない」は、「課題解決に向かっていく論理的な話ができない」という不満であることが多いんです。
「女性のいう「話し合いにならない」は、「私の感情に私と同じくらいの気持ちで向き合ってくれない」だし、男性のいう「話し合いにならない」は、「課題解決に向かっていく論理的な話ができない」なんです。」
引用元記事:「話し合いができない彼氏、彼女のいるあなたへ。解決策はこれだ!」
このギャップを埋めるためには、まず相手のコミュニケーションスタイルを理解することから始めましょう。
相手が黙り込むタイプなら、「考えるのに時間がかかる人」かもしれません。世の中には、答えをパッと出せる回転の早い人もいれば、納得するまでじっくり考えてからでないと答えを出せない熟考型の人もいるんですね。
相手が感情的になりやすいタイプなら、「自分の意見を否定されることに敏感な人」かもしれません。些細な意見の相違でも、自分自身が否定されたように感じてしまう人もいます。
共感にも「情動的共感」と「認知的共感」という2種類があることを知っておくと、より相手を理解しやすくなります。
情動的共感は「心から同じ気持ちになって一緒に泣いてあげる」という共感で、認知的共感は「状況を把握した上で『あなたはそう感じるんだね』と相手を理解する」という共感です。
女性は情動的共感を得意とする人が多く、男性は認知的共感が得意な人が多い傾向があります。
「認知的共感って、一種の「状況把握」なんですね。もちろんただ機械的に実況見分しちゃダメですよ(笑)ただ、例えば女性側が「仕事を辞めたい」と打ち明けてきた時に、認知的共感をしようとすると相手の立場を理解する必要があるので、「辞めたいって思うってことは、なにかあったの?」という質問が出てくると思うんです。」
引用元記事:「話し合いができない彼氏、彼女のいるあなたへ。解決策はこれだ!」
また、「選択的注意」という現象も理解しておくと役立ちます。
人は自分が普段から意識していることに注意が向きやすいものなんです。
「言い方」を意識している人は相手の言い方に敏感になりますし、「成果」ばかり意識している人はタスクの達成度に目が行きます。
そして大切なのは、これらの違いを「欠点」と捉えるのではなく、「個性の違い」として尊重する姿勢です。
私たちは皆、生まれ育った環境や経験から独自のコミュニケーションスタイルを身につけてきました。相手のスタイルを理解し、尊重することが、より良い関係への第一歩となるでしょう。
相手と自分のコミュニケーションスタイルの違いを理解できれば、「なぜ分かり合えないのか」という謎が少しずつ解けていくかもしれませんね。
話し合いの場と時間を適切に選ぶコツ

大切な話し合いがうまくいかない理由の一つに、「場と時間の選び方」があることをご存知でしょうか?
相手の状態や環境によって、同じ内容の話でも受け取り方が大きく変わることがあるんです。
話し合いの場と時間を適切に選ぶことは、コミュニケーションをスムーズに進めるための重要なポイントになります。
まず考えたいのが、相手の疲労度や気分です。
仕事で疲れて帰宅したパートナーに、「今から話し合いましょう」と切り出しても、「もう休ませてくれよ」という気持ちになるのは自然なことです。
くつろげるはずの我が家に帰ってきた直後に重要な話をされると、うんざりしてしまう人も多いんですね。
「夫が疲れて会社から帰宅した後に「今から話し合いましょう」と言っても、夫は「もう休ませてくれよ」という気持ちになります。くつろげるはずのわが家に帰ってきた途端に面倒な話をされ、うんざりする夫もいるでしょう。」
引用元記事:「夫が話し合いから逃げる!将来が心配…」
話し合いを始める前に、「今、15分くらい話せる?」と確認することも大切です。
心の準備ができていない相手にいきなり話をスタートすると不調に終わりがちなので、「週末でもいいけどどう?」と予約しておくのも一つの方法です。
場所の選び方も重要なポイントです。
自宅では家事や子供の相手などで話が中断されやすかったり、相手が気が乗らないときの逃げ場が多かったりします。
時には自宅とは違う環境、例えばカフェやレストランなどで落ち着いて話すことで、新たな視点が生まれることもあるんですよ。
「自宅では家事や子供の相手などで話が中断されやすく込み入った話が最後までできなかったり、夫が気が乗らないときの逃げ場もたくさんあります。一時預かりなどが利用できるなら、夫婦だけでカフェやレストランなどで落ち着いて話すのもおすすめです。」
引用元記事:「ウチの夫は「話し合い」ができない男!?3つのタイプと対処方法」
特に話し合いが難しいパートナーとの場合、伝達手段を変えてみるのも効果的です。
直接話すと感情的になってしまうようなテーマであれば、スマホのメッセージアプリやメールなど、文字でのコミュニケーションを選ぶことで、冷静に本題だけを伝えられることもあります。
また、「いつまでに決めたい」というリミットを伝えることも、話し合いを進めるコツの一つです。
「住宅ローン減税の終了が今年の9月」といった明確な日時や、「将来のことを考えたら、35歳までに第2子を出産したい」といった自分なりのリミットを伝えることで、相手も状況の重要性を理解しやすくなります。
そして忘れてはならないのが、話し合いのゴール設定です。
必ずしも「結論を出すこと」がゴールである必要はありません。
特にすぐに結論が出ないような内容であれば、まずは「相手の思いを理解する」だけでも十分立派なゴールになり得ます。
「今日はとりあえず相手の気持ちを聞くところまでにしよう」と考えることで、むやみに結論を急いだり、思い通りにならずにイライラしたりすることも減るかもしれませんね。
話し合いの場と時間を適切に選ぶことは、相手への思いやりの表れでもあります。少しの工夫で、お互いの理解が深まり、より良い関係づくりにつながるかもしれません。
具体的に伝える・質問する方法
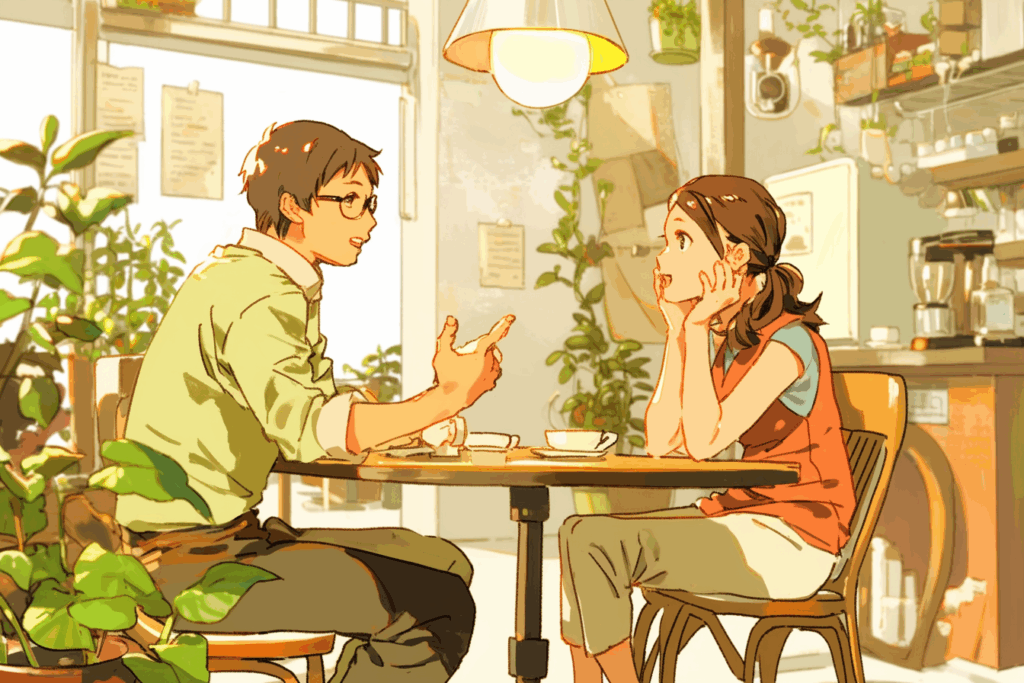
パートナーとの話し合いがいつも平行線になってしまうとき、もしかしたらコミュニケーションの方法自体に課題があるのかもしれません。
とくに「話し合いができない」と感じるパートナーとの会話では、伝え方や質問の仕方を工夫することで、大きく状況が変わることがあるんです。
まず大切なのは、抽象的な表現ではなく具体的に伝えることです。
共感思考の強い女性は、課題解決思考の男性に「もっと配慮して欲しい」「ちゃんとしてほしい」「普通こうじゃない」といったぼやっとした要望を伝えがちです。
しかし、こうした表現は男性からすると「抽象的すぎて意味がわからない」と感じることが多いんです。
「課題解決思考の男性がいざ解決をしようと「じゃあ、どこが気に入らないの?どうしたらいいの?」と聞くと、具体的なアドバイスが出てこないことが多くて、それがより溝を深くしていたりします。よくあるのが、「もっと配慮して欲しい」「ちゃんとしてほしい」「普通こうじゃない」とぼやっとした要望しか伝えられないケース。これだと男性からすると、「抽象的すぎて意味がわからない」と感じます。」
引用元記事:「話し合いができない彼氏、彼女のいるあなたへ。解決策はこれだ!」
「もっと」とか「普通は」と言われると、男性側からするとふわっとしすぎていて混乱してしまいます。
代わりに、「語尾はこうしてほしい」「こういうタイミングでこういう発言はやめて欲しい」など、より具体的な指示を心がけましょう。
また、質問の仕方も工夫することで、相手の本音を引き出しやすくなります。
例えば「この問題についてどう思う?」という漠然とした質問よりも、「この2つの選択肢のうち、どちらが良いと思う?」と具体的な選択肢を示す方が答えやすいですね。
そして、質問をするときは「正解を探す」のではなく「相手の考えを知りたい」という姿勢で臨むことが大切です。
「なぜそう思うの?」と問いつめるように聞くと、相手は防衛的になってしまいます。
代わりに「そう考えるのはどんな理由からかな?」と柔らかく尋ねると、相手も答えやすくなるでしょう。
特に黙り込みがちな相手には、「YES・NO」で答えられる質問から始めるのも効果的です。
「今日の夕食、和食と洋食どちらがいい?」のように具体的な選択肢を示すことで、答えるハードルを下げられます。
そして、質問した後は「待つ」ことも重要なポイントです。
黙る人は、もともと口が重かったり慎重だったりする人が多いです。
そのため、話し出すのに少し時間がかかります。その数十秒を待つことなくまくし立ててしまっては、一向に意見を聞きだせません。
「ゆっくりでいいから意見を教えて?」「待っているから聞かせてほしい。」などと時間をかけて聞いてあげましょう。途中で遮ったり急かしたりしてはいけません。
引用元記事:「「黙る人」に共通する「8つの心理」とは」
また、伝える内容が相手にとって受け入れづらいものである場合は、「サンドイッチ法」を試してみるのも良いでしょう。
これは相手へのポジティブなフィードバック→改善してほしいこと→再度ポジティブなフィードバックという順序で伝える方法です。
例えば「いつも家事を手伝ってくれて助かってるよ。でも、食器を洗った後の水切りのやり方を少し変えてもらえると嬉しいな。いつも協力的でありがとう」といった具合です。
さらに、自分の気持ちを「私メッセージ」で伝えることも効果的です。
「あなたはいつも〜する」という相手を主語にした文ではなく、「私は〜と感じる」という自分を主語にした文で伝えることで、相手は批判されていると感じにくくなります。
具体的に伝え、質問する方法を工夫することで、これまでうまくいかなかった話し合いが、少しずつ変わっていくかもしれません。
コミュニケーションは一朝一夕に変わるものではありませんが、小さな変化の積み重ねが大きな変化につながることもあるのではないでしょうか。
認知的共感と情動的共感の使い分け
パートナーとの話し合いでなかなか分かり合えず、「この人には共感能力がないのかも」と悩んだことはありませんか?
前に話した通り、共感には「情動的共感」と「認知的共感」という2つのタイプがあるんです。
この違いを理解すると、相手とのコミュニケーションがぐっと楽になるかもしれません。
情動的共感とは、「心から同じ気持ちになって一緒に泣いてあげる」という共感です。
相手の感情に自分も同じように反応し、喜びや悲しみを分かち合うんですね。
認知的共感は「状況を把握した上で『あなたはそう感じるんだね』と、相手のことを理解する」というもの。感情そのものを共有するのではなく、相手の立場や気持ちを知的に理解するアプローチです。
「情動的共感というのは、「心から同じ気持ちになって一緒に泣いてあげる」という共感です。一方認知的共感というのは、「状況を把握した上で「あなたはそう感じるんだね」と、相手のことを理解する」というものなんですよね。」
引用元記事:「話し合いができない彼氏、彼女のいるあなたへ。解決策はこれだ!」
面白いことに、女性は「情動的共感」が得意な人が多く、男性は「認知的共感」が得意な人が多い傾向があるようです。
これはパートナーとの話し合いの際に大きなギャップを生み出すことがあります。
女性が悩みを打ち明けたとき、同じ気持ちになって共感してほしいのに、男性はすぐに解決策を提案しようとする…。このようなことです。
妊娠出産に対する男性の「共感」が足りないという女性からの主張でよく見られるのが「夜泣き対応」の問題です。
深夜に起きて寝不足の中でミルクをあげている時、パートナーにも一緒に起きてそばにいてほしいと思う女性が多いんです。
「それってお互い寝不足になるだけじゃない?」と思う人もいるかもしれませんが、共に苦しいことや辛いことを同じ気持ちで共有してほしいという「情動的共感」を求めているんですね。
一方で、「情動的共感」は物事の解決には必ずしも役立たないこともあります。
カウンセリングの現場でも、「情動的共感」だけでは相談者が前に進めないことが多いそうです。
本当に大事なのは「認知的共感」だと言えるかもしれません。
認知的共感とは、一種の「状況把握」です。
相手が「仕事を辞めたい」と打ち明けてきたとき、「辞めたいって思うってことは、なにかあったの?」と質問することで、相手の立場を理解しようとする姿勢を示せます。
男性からすると単に状況を理解するために聞いているだけかもしれませんが、女性からするとその質問こそが「わかろうとしてくれている」と感じるきっかけになるんですね。
では、より良いコミュニケーションのために、どう共感を使い分ければいいのでしょうか?
女性は男性に対して情動的共感を期待しすぎないことが大切かもしれません。
男性が得意とする認知的共感での理解を受け入れ、それを「共感してくれていない」と誤解しないようにすることで、お互いの理解が深まるでしょう。
一方、男性は「俺は共感なんてできない」と諦めるのではなく、認知的共感をする努力をすることが大切です。
相手の話をじっくり聞き、「そう思うんだね」「そういう気持ちだったんだね」と理解を示すことが、パートナーとの関係をより豊かにしてくれるでしょう。
共感のタイプの違いを理解することは、お互いへの期待値を適切に設定することにもつながります。期待とのギャップが小さくなれば、関係はもっと楽になるかもしれませんね。
情動的共感と認知的共感、どちらも大切なコミュニケーションのツールです。
状況や相手に合わせて使い分けることで、より豊かな人間関係を築いていくことができるのではないでしょうか。
自分自身が黙るタイプの人の改善策
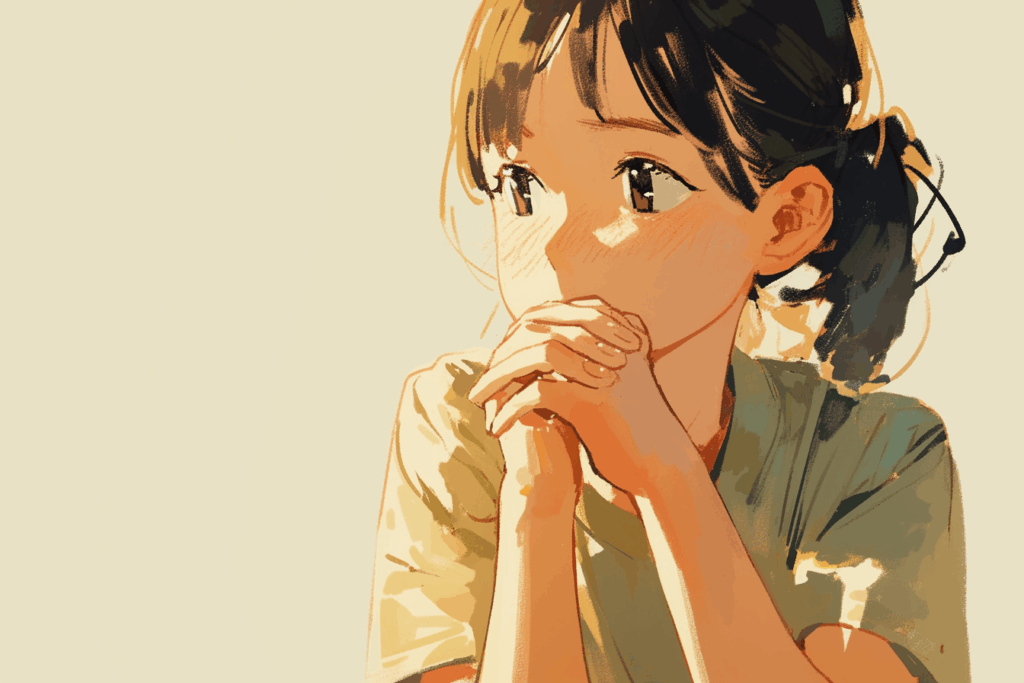
あなた自身が話し合いの場で黙りがちだと感じることはありませんか?
相手から「なんで黙るの?」「どう思っているのか教えて」と言われても、なかなか言葉にできなかったり、返事ができなかったりすることがあるかもしれません。
実は、自分の気持ちを表現するのが苦手な理由はさまざまで、小さい頃からの環境や経験が大きく影響していることもあるんです。
自分自身が黙るタイプだと気づいたなら、まずはその理由を探ってみることから始めてみましょう。
黙ってしまう原因の一つには、「自分の気持ちに鈍感」という特徴があります。
小さい時から「自分の気持ちを伝えてこなかった人」「自分の本当の気持ちを後回しにしてきた人」にありがちですが、自分の気持ちが分からないから返事ができなくなってしまうんです。
「嫌だ」「イライラ」する気持ちは出てくるのに、「具体的に何が嫌だったか」がすぐには分からないという状態です。
「自分の気持ちに鈍感ってどういうこと?って思う方もいらっしゃるかもしれません。でも、小さい時から「自分の気持ちを伝えてこなかった人」「自分の本当の気持ちを後回しにしてきた人」「自分の気持ちを知ろうとしなかった人」にありがちですが、自分の気持ちが分からない、だから返事ができなくて黙り込んでしまうんです。」
引用元記事:「話し合いや喧嘩で黙る人の心境」
また「思考停止してしまう」こともよくある原因です。
時間をかけて考えを整理したいタイプなのに、すぐに返答を求められると思考が止まってしまうんですね。
あるいは「自分の気持ちを伝えずに自己解決している」ケースも。
自分の意見を言うことで相手が傷つくのではないかと考え、一人で解決しようとしてしまうことがあります。
では、黙りがちな自分を変えるためには、どんな工夫ができるでしょうか?
まず一つ目のポイントは、「考える時間もらってもいい?」と伝えることです。
すぐに返答できない時、黙り込んでしまうことがあると思いますが、相手からしたら「なんで黙っているのか?」分からないんです。
「もう話したくないのか?」「放棄したのか?」「考えているのか?」が伝わらず、相手も困ってしまいます。
「すぐに返答できない時、黙り込んでしまうことがあると思いますが、相手からしたら「なんで黙っているのか?」分からないんです。(「もう話したくないのか?」「放棄したのか?」「考えているのか?」)だから、まずは「考えている」と「返事を後にしたい」ことを伝える。それだけで、相手はアクションがわかって安心します。」
引用元記事:「話し合いや喧嘩で黙る人の心境」
まずは「考えている」と「返事を後にしたい」ことを伝えるだけでも、相手は安心できるでしょう。
二つ目のポイントは、「判断するのは相手。自分の意見を伝えることが重要」だと理解することです。
「傷つけるんじゃないか?」「言っても無駄」と自己判断して黙ってしまうことがありますが、それは本当に相手のためになっているでしょうか?
自分が我慢すればいいという考えは、どこかで爆発してしまう可能性もあります。
まずは自分の意見を伝えてみて、その後どうするかは相手に委ねてみるのもいいかもしれません。
三つ目のポイントは、普段から「自分の気持ちを言語化する」練習をすることです。
「モヤモヤ」「イライラ」「嬉しい」「悲しい」といった気持ちを感じたときに、具体的に何にそう感じたのかを言葉にしてみましょう。
これは簡単なことではありませんが、少しずつ練習を重ねることで、自分の気持ちを表現する能力は必ず向上します。
ノートに書き出してみる、信頼できる人に話してみる、SNSに投稿してみるなど、自分に合った方法で始めてみると良いでしょう。
変化は一朝一夕には訪れませんが、少しずつ自分の声を取り戻していくことで、より豊かなコミュニケーションが可能になるはずです。
そして何より、自分を責めすぎないことも大切です。黙るタイプの人は、自分のコミュニケーションスタイルを「欠点」と捉えがちですが、それぞれの人にはそれぞれの個性があります。
自分らしさを大切にしながら、少しずつ変化を目指していくことが、長い目で見たときの成長につながるのではないでしょうか。
話し合いの目標設定を見直す柔軟さ
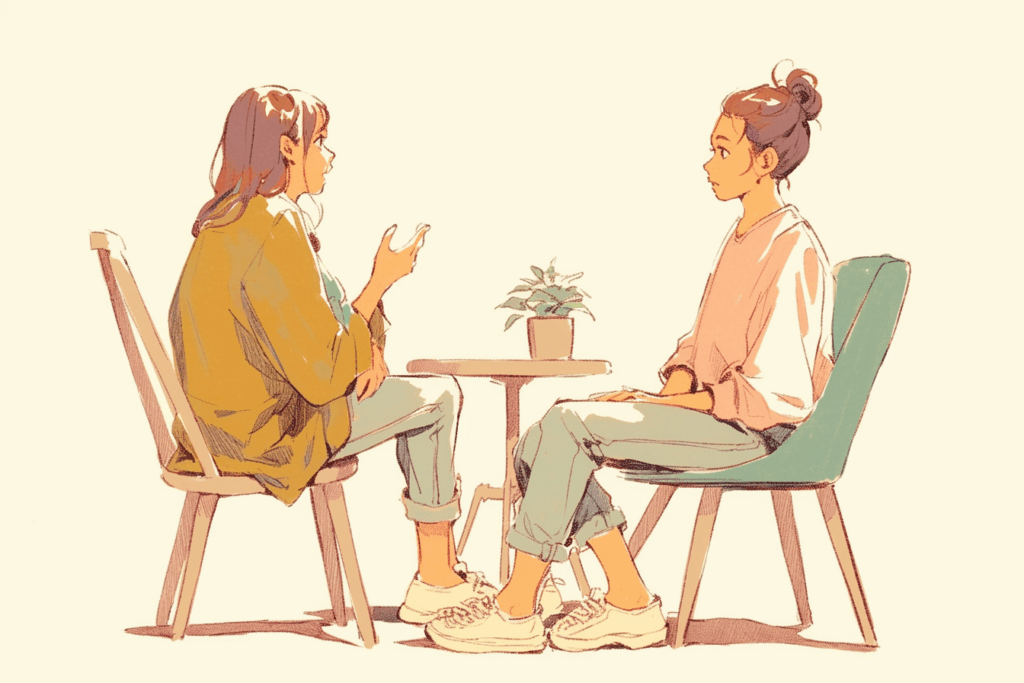
パートナーとの話し合いで、いつも納得のいく結論に至らないことで悩んでいませんか?
もしかしたら、それは「話し合いの目標設定」自体を見直す時期かもしれません。
私たちは無意識のうちに、話し合いの目標を「自分の意見を通すこと」や「相手の意見を変えること」に設定しがちです。
しかし、そもそも話し合いの本当の目的とは何でしょうか?
話し合いのゴールは、実はさまざまです。
自分の言い分が通ること、相手の言い分を受け入れること、2人の中間地点を見つけること…一般的にはこれらのいずれかだと考えられます。
「「話し合い」のゴールはなんだと思いますか?自分の言い分が通ること、相手の言い分を受け入れること、2人の中間地点を見つけること…一般的には、そのいずれかだと考えられます。」
引用元記事:「ウチの夫は「話し合い」ができない男!?3つのタイプと対処方法」
しかし、特にすぐには結論が出ないような内容であれば、まずは「相手の思いを理解する」だけでも立派なゴールになり得るんです。
ゴールの設定を変えてみると、「今日はとりあえず相手の気持ちを聞くところまでにしよう」と考えることもでき、むやみに結論を急いだり、自分の思い通りにならずにイライラしたりすることも少し減るのではないでしょうか。
相手が黙り込むタイプの場合、「話し合って決める」という目標設定自体が難しいかもしれません。
そんなときは「黙っている=相手に意見はなし、全権を委ねられた」と理解して、あなたが主導権を握って物事を進めてみるのも一つの方法です。
生活の中の小さなことで意見が食い違ったときに、相手が黙り込んでいるならば、「じゃあ今度からはこうするからね。異論があるなら受け付けるよ!」と一方的に宣言してしまうのです。
それは嫌だ、おかしいと思えば、相手も反論してくるでしょう。
また、話し合いという名目で、実際には「同意の強制」「ダメ出し」「謝罪要求」「ケンカを売る」といったことをしていないか、見つめ直してみることも大切です。
「最後に、夫がすぐ逃げる、キレる、黙る…話し合いにならない!とモヤモヤしているとき、見直してみたいことがあります。「話し合い」という名目で、その実、以下のようなことをしていないでしょうか。同意の強制、ダメ出し、謝罪要求、ケンカを売る」
引用元記事:「ウチの夫は「話し合い」ができない男!?3つのタイプと対処方法」
もし、相手の意見を聞き、どういう気持ちなのかを知り、どうしたらいちばんいいのか一緒に考えるつもりであれば、上記のような場合は「話し合おう」ではなく、「これはお願いなんだけど…」「いつもありがとう、でも1つだけどうしても気になるから聞いてくれる?」といった言葉に置き換わるのではないでしょうか。
話し合いの形式にこだわらず、「形でなくとも、改善があれば良し」とする柔軟な姿勢も時には必要です。
「子供と遊ぶときはスマホ片手じゃなく向き合ってほしい」と伝えたのに相手が「うーん」と生返事だったとしても、次回それを思い出してスマホを置く姿が見られれば、まずは一歩前進ですよね。
特に相手が口下手な場合、言葉での応答は少なくても、行動で示してくれることがあります。
「あ、話を聞いてくれてるんだ」と気づくだけでも、かなりストレスが減るかもしれません。
さらに、話し合いのテーマによっては、「一度に解決しなくてもいい」と期間を区切ることも有効です。
「いつまでに決めたい」というリミットを伝えることで、相手も考える時間が持てますし、言いたいことを整理する余裕も生まれます。
「住宅ローン減税の終了が今年の9月」といった明確な日時でも、「35歳までに第2子を出産したい」という自分なりのリミットでも構いません。
話し合いの目標設定を柔軟に変えることで、これまでうまくいかなかった話し合いが、少しずつ変化していくかもしれません。
相手の特性を理解し、状況に応じた目標設定をすることで、より建設的な関係づくりにつながるのではないでしょうか。
話し合いができない人が黙る理由と対処法
- 女性は共感思考、男性は課題解決思考をする傾向があり、話し合いの目的が異なる
- 「逃げる・ごまかす」タイプは疲れや不利な結果への予測から話し合いを避ける
- 「黙り込む」タイプは口論が苦手で温和だが、嫌なことを言えない特徴がある
- 「キレる・怒り出す」タイプは自分の考えだけが正しいと思い込む傾向がある
- 黙る人は「嫌われたくない」「こらえている」などの心理状態にある
- 黙るタイプの人は自分の気持ちに鈍感で何が嫌なのか言語化できないことがある
- 相手のペースに合わせて話すスピードやリズムを調整することが重要
- ゆっくり聞き出す姿勢を持ち、相手が考える時間を持てるよう余裕を持つ
- 話し合いの前に時間と場所をはっきり伝え、テーマを明確にする
- 伝達手段を変え、メッセージアプリなど文字でのコミュニケーションも検討する
- 抽象的な表現ではなく具体的に伝えることで男性の理解を促進できる
- 情動的共感(感情共有)と認知的共感(知的理解)を状況に応じて使い分ける
- 黙る自分を変えるには「考える時間をもらう」と伝えることから始める
- 話し合いのゴールを「相手の思いを理解する」などと柔軟に設定する
- 相手の特性を理解し、関係づくりより効果的な目標設定をする