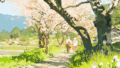職場にはいろいろなタイプの上司がいますが、中でも記憶力が悪い上司との仕事は、なかなか気を遣うものです。
昨日話したことをすっかり忘れられていたり、指示が毎回変わったりすると、こちらのストレスも限界に達します。
とはいえ、毎回イライラしても状況は変わりません。
大切なのは、自分の仕事を守りながら、うまく付き合うための工夫をすることです。
記憶力が悪い上司に振り回されないようにするためには、記録を残す・伝え方を工夫する・チームで情報を共有するなど、いくつかの実践的なポイントがあります。
この記事では、記憶力が悪い上司との仕事をスムーズに進めるための具体的な方法と、ストレスを減らす考え方を紹介します。
- ・記憶力が悪い上司に効果的な報告・連絡・相談のコツ
- ・トラブルを未然に防ぐ記録術と見える化の実践方法
- ・コミュニケーションで信頼関係を築くテクニック
- ・ストレスをためないための上司との付き合い方の工夫
記憶力が悪い上司に振り回されないための仕事の工夫
記憶力が悪い上司と一緒に働くと、仕事の進行に支障が出たり、ストレスがたまりがちです。ですが、いくつかの工夫を取り入れることで、自分の仕事を守りつつ、スムーズなやりとりを実現することが可能です。
以下は、記憶力が悪い上司との仕事を円滑にするための実践的な工夫です。
- 記憶力が悪い上司には「証拠を残す」が鉄則
- 指示が変わる上司には「見える化」で対応
- 会話を記録する習慣で「言った言わない」を防ぐ
- チーム全体で情報を共有して混乱を防止する
記憶力が悪い上司には「証拠を残す」が鉄則
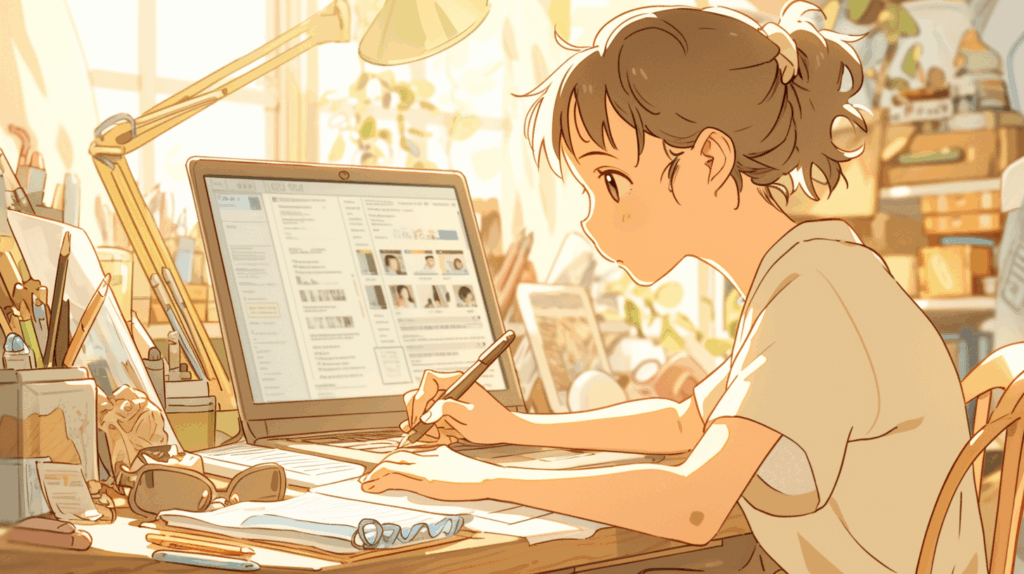
記憶力が悪い上司には、口頭でのやりとりだけに頼らず、必ず文書やデジタルで「証拠」を残すことが重要です。
たとえば、会話のあとに「さきほどのお話についてまとめました」とメールで要点を送るだけでも、後々のトラブル防止になります。
SlackやTeamsなどのチャットツールを活用すれば、時系列でも確認でき、上司も後で振り返りやすくなります。
記録が残っていれば、指示の変更があっても「前はこういう内容でしたよね」と冷静に伝えることができます。
これにより、自分の責任を明確にしつつ、上司のフォローも可能になります。
特に、締切や重要な要件については、事前・事後の両方で記録をとることが、信頼関係を崩さずに自分を守るポイントです。
指示が変わる上司には「見える化」で対応
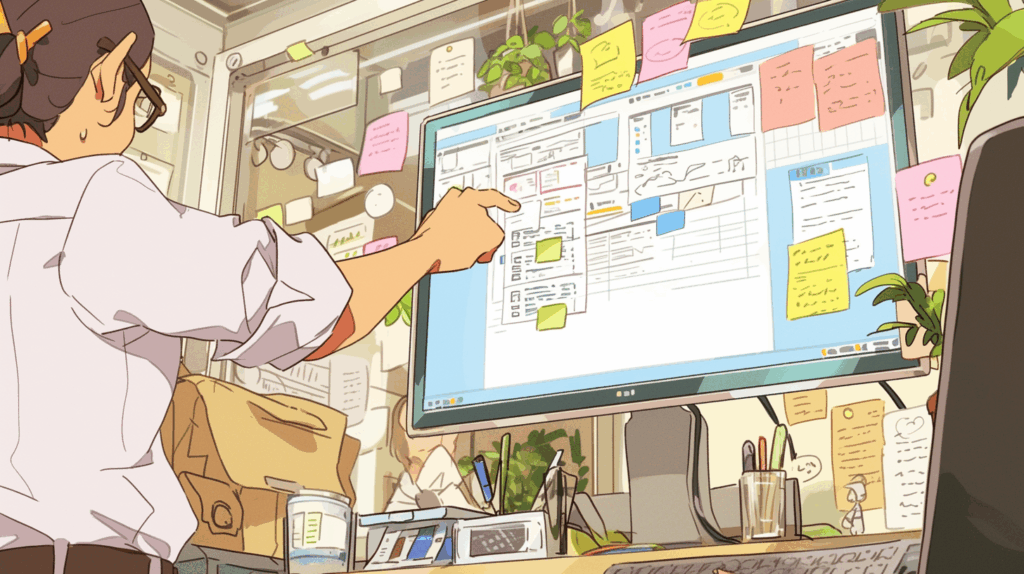
記憶力が悪く、指示が二転三転する上司には、「見える化」がとても効果的です。
ホワイトボードやプロジェクト管理ツール(例:Trello、Notion、Backlogなど)に現在のタスクと進行状況を明示することで、上司自身も混乱しにくくなります。
また、共有スプレッドシートに業務内容や期日を一覧化し、関係者全員が見られるようにしておけば、「そんな話は聞いてない」といった行き違いも回避できます。
上司が忘れたときに「こちらのシートに記載してあります」と示すことができるため、言い争いになりにくいというメリットもあります。「
見える化」は、自分のためだけでなく、上司や他のメンバーにとっても、安心感と信頼を高める有効な手段です。
会話を記録する習慣で「言った言わない」を防ぐ
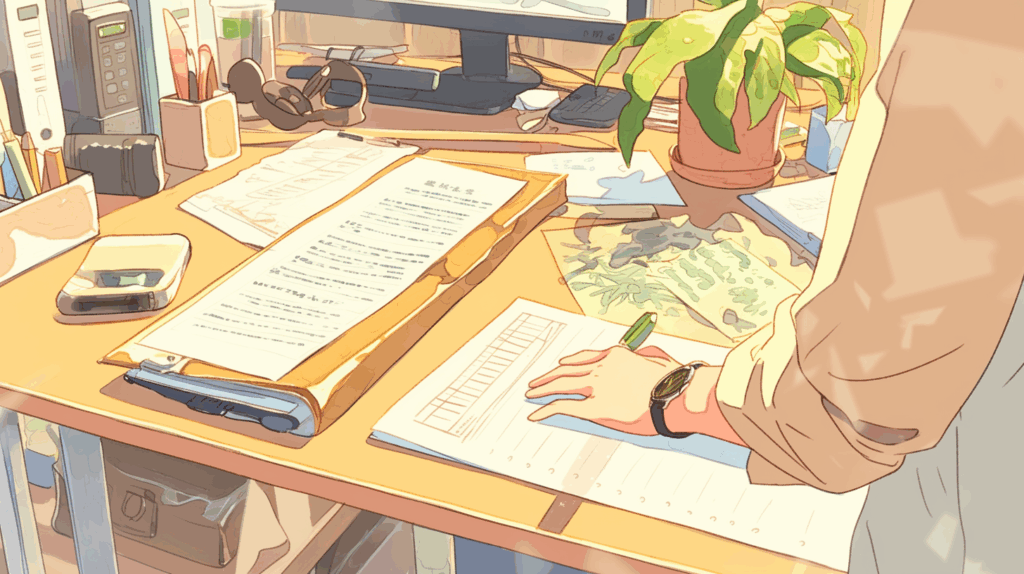
記憶力が悪い上司との会話は、忘れられる前提で対応するのが基本です。
頭でのやり取りは、できるだけその場でメモを取り、話が終わったあとに内容を簡潔にまとめたメモやメールを送りましょう。
「確認のためにまとめました」といった言い回しにすると、相手にも失礼になりません。
また、社内チャットツールでの報連相も記録が自動で残るため、会話よりも文章を意識的に使うようにするのがおすすめです。
場合によっては、上司との1対1の打ち合わせも録音の許可を得た上で活用するのも手段の一つです。
記録があれば、自分の立場を守るだけでなく、上司の勘違いを優しく正すこともできます。
トラブルを避けるには、「証拠」を日常的に残す習慣が大きな武器になります。
チーム全体で情報を共有して混乱を防止する
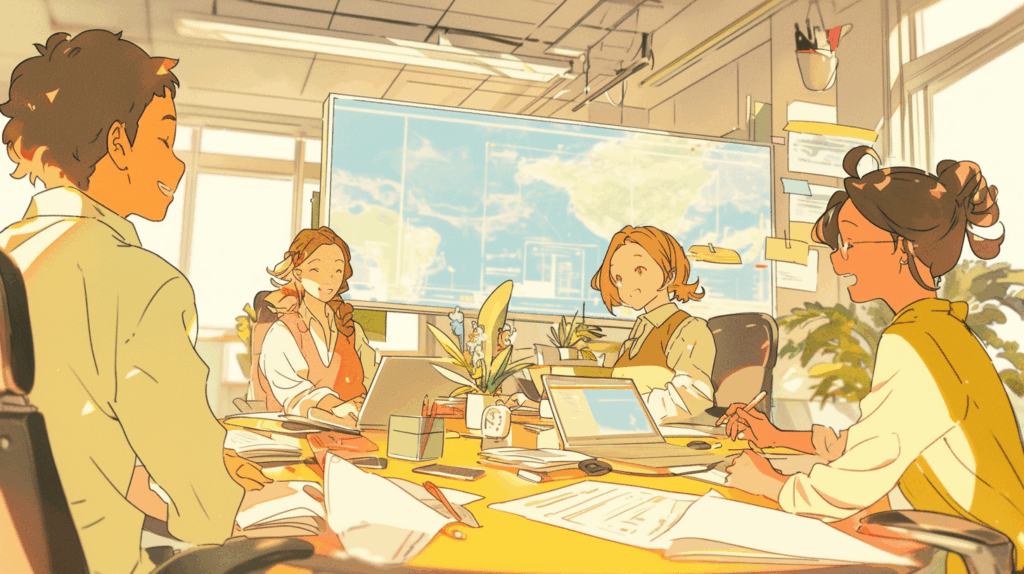
上司が記憶力に課題を抱えている場合、個人だけで対応しようとすると限界があります。
そこで重要なのが、チーム全体での情報共有です。
チーム内で打ち合わせ内容や業務状況をまとめた共有ドキュメントを作成しておけば、誰が何を把握しているのかが可視化され、上司が忘れてしまっても周囲がサポートしやすくなります。
また、定例ミーティングを設定し、毎回の内容を議事録として残すことも有効です。
上司だけでなく、他のメンバーが情報を補完できる体制が整っていれば、業務の流れが止まるリスクも減ります。
全員でフォローし合うことで、チームの信頼関係も深まり、記憶力の課題があっても円滑に仕事が進むようになります。
記憶力が悪い上司とうまく付き合うためのコミュニケーション術
記憶力が悪い上司との関係性は、こちらの伝え方や距離感で大きく変わります。ストレスを減らしながらうまく付き合うためには、効果的なコミュニケーションの工夫が欠かせません。
ここでは、記憶力が悪い上司とうまく連携するためのポイントを紹介します。
- 上司の記憶力をサポートする伝え方とは?
- 忘れっぽい上司に効果的なフォローアップメール
- 上司の特徴を理解してストレスを減らすコツ
- 無理せず付き合うための「割り切り」も必要
上司の記憶力をサポートする伝え方とは?
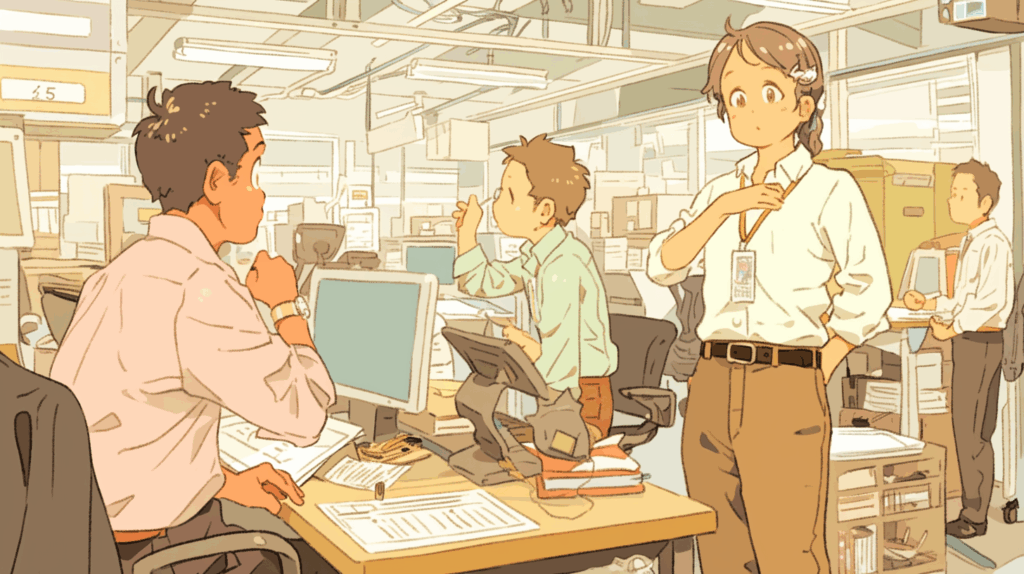
記憶力が悪い上司に対しては、伝え方を工夫することがとても重要です。
ポイントは「短く・具体的に・繰り返す」こと。情報が多すぎると混乱しやすくなるため、重要な部分だけを簡潔に伝えるようにしましょう。
たとえば、「この件は、〇日までに完了予定です」と期限を明確にするだけでも、相手の理解がスムーズになります。
また、同じ内容を時間をおいて繰り返し伝えることで、記憶の定着を助けることができます。
話すだけでなく、簡単な図や表を使うのも効果的です。
上司の理解度に合わせて伝え方を柔軟に変えることが、良好な関係づくりにつながります。
忘れっぽい上司に効果的なフォローアップメール
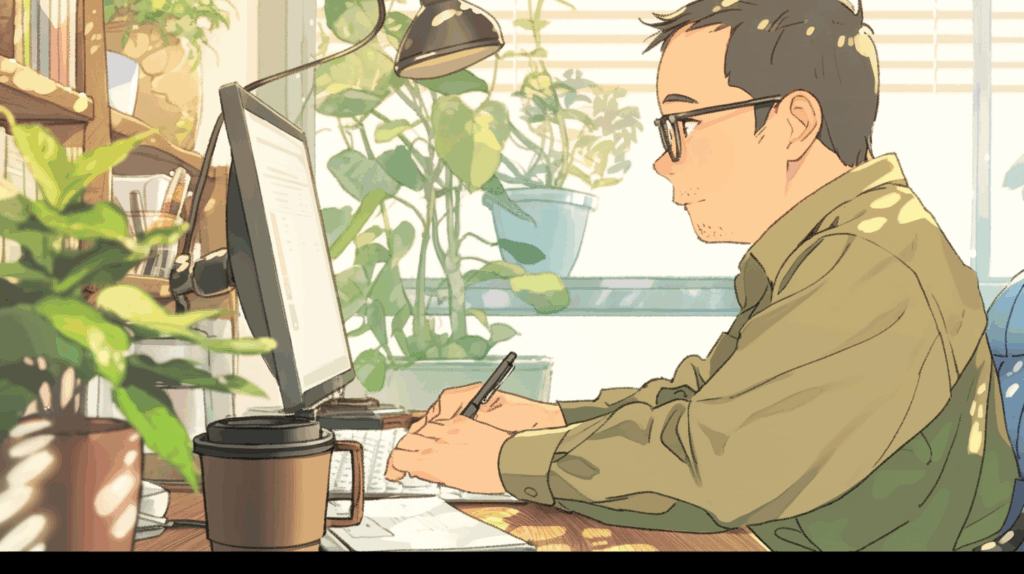
忘れっぽい上司には、会話後に送るフォローアップメールが強力な武器になります。
「本日の打ち合わせのまとめです」「次回までにこちらを進めます」といった形で、やるべきことと背景を簡潔に書くのがポイントです。
口頭では伝わらなかったことも、メールで書かれると記録として残り、あとで確認できる安心感があります。
また、本文の最後に「この内容で問題があればご指摘ください」と一言添えることで、相手に確認を促すと同時に、自分の保身にもつながります。
メールは、言った言わない問題を防ぐだけでなく、信頼の積み重ねにもなります。
毎回のやり取りを丁寧に残すことで、仕事の精度も自然と上がっていきます。
上司の特徴を理解してストレスを減らすコツ
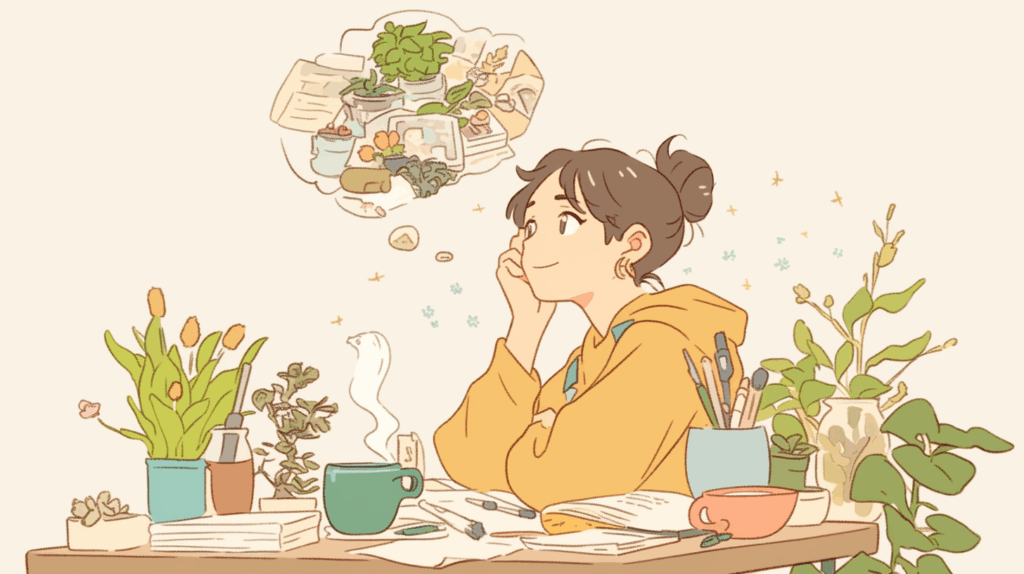
記憶力が悪い上司に対してイライラするのは当然の反応ですが、少し視点を変えて「この上司はこういう人」と理解することで、自分のストレスは大きく減らせます。
たとえば、細かい指示を忘れるけれど大まかな方向性は間違っていない、といったように、上司の得意・不得意を把握しておくと、対応もしやすくなります。
また、「忘れることを責めても変わらない」と割り切って考えることで、自分の感情をコントロールしやすくなります。
期待値を下げることで、余計なストレスから解放され、冷静な対応ができるようになります。
職場は感情より結果が大切です。ストレスを溜めず、割り切ることも一つのスキルです。
無理せず付き合うための「割り切り」も必要
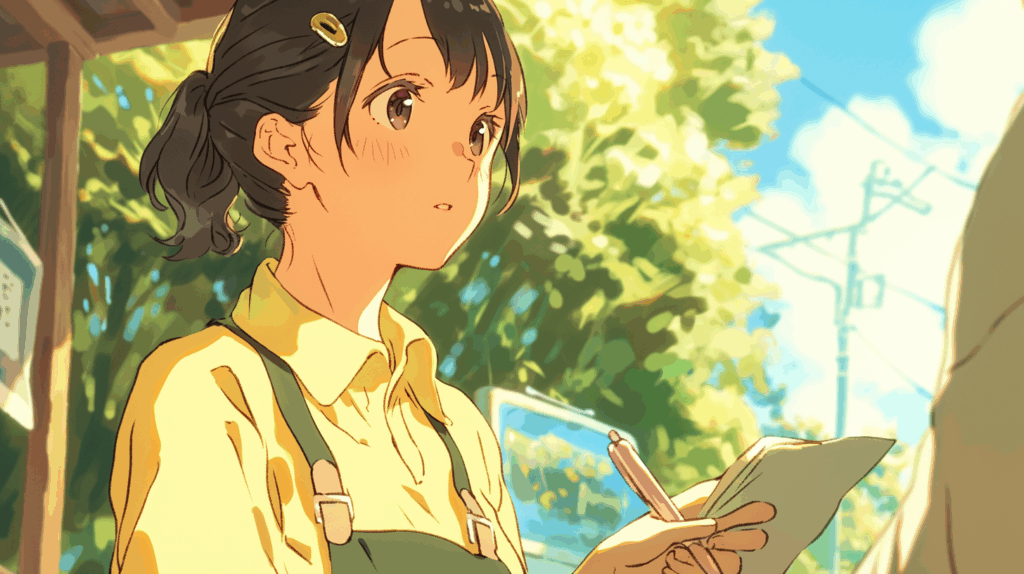
記憶力の悪い上司と無理に信頼関係を築こうとすると、こちらが疲れてしまうこともあります。
そこで重要なのが「割り切る」という考え方です。
「この人は忘れる人」と前提を持って接することで、いちいち驚いたりイライラすることが減ります。
たとえば、何度も同じ説明を求められても、「毎回初回だと思って説明しよう」と気持ちを切り替えれば、感情を消耗せずに済みます。
また、自分ができる範囲で対応し、それ以上は他の人に任せたり、共有して抱え込まないようにすることも大切です。
無理せず距離を保つことで、自分の心身の健康を守ることにもつながります。
職場では「適度な諦め」も円滑な関係の鍵です。
まとめ
記憶力が悪い上司と仕事をするうえで大切なのは、イライラを我慢するのではなく、具体的な対策を取ることです。
記録を残す・伝え方を工夫する・無理せず付き合うなど、日常の中でできる工夫で、大きなストレスやトラブルを防ぐことができます。
自分を守りながら、周囲とも連携し、前向きに仕事を進める力を身につけましょう。
- 記憶力が悪い上司には「証拠を残す」が鉄則
- 指示が変わる上司には「見える化」で対応
- 会話を記録する習慣で「言った言わない」を防ぐ
- チーム全体で情報を共有して混乱を防止する
- 上司の記憶力をサポートする伝え方とは?
- 忘れっぽい上司に効果的なフォローアップメール
- 上司の特徴を理解してストレスを減らすコツ
- 無理せず付き合うための「割り切り」も必要