「うちの子、最近なんだかおかしい…」
小学5年生のお子さんを持つ親御さんなら、一度はそう感じたことがあるかもしれませんね。
昨日まで素直だったのに、急にひどい口答えをしたり、無視をしたり。男の子も女の子も、その態度の変化に「この反抗期はいつまで続くの?」と不安になるのは当然です。
特に、物を壊す、嘘をつくといった行動が見られると、親としてはどう対応していいかわからず、疲れたと感じてしまうこともあるでしょう。
私も、子どもの反抗的な態度に悩み、親としての対応でやってはいけないことは何だろう、と日々模索していました。
過度な干渉は避けたいけれど、親への暴力に発展したら…と心配は尽きませんよね。
この時期の子どもとの関わり方は、本当に難しい問題だと思います。
しかし、この一見問題に見える行動は、お子さんが心身ともに大きく成長している証でもあります。
この記事では、そんな悩める親御さんに向けて、ひどいと感じる5年生の反抗期の原因から、具体的な接し方、そして専門家への相談を考えるべきサインまで、私の経験も踏まえながら、少しでも心が軽くなるような情報をお届けできればと思います。
5年生の反抗期が「ひどい」と感じる原因と男女別の特徴
反抗期の子どもに絶対やってはいけない親のNG対応
親子関係を悪化させないための具体的な接し方とルール作り
専門家への相談を検討すべき危険なサインと相談窓口
5年生の反抗期がひどい原因と特徴

小学5年生、10歳という年齢は、子どもが心身ともに大きく変化する「おとなへの入り口」です。
この時期に見られる反抗的な態度は、単なるわがままではなく、成長に伴う複雑な心理が隠されています。
まずはその原因と特徴を理解することから始めましょう。
いつまで続く?中間反抗期とは
「この反抗期、一体いつまで続くの…?」と途方に暮れてしまう気持ち、よくわかります。一般的に、小学5年生頃の反抗期は「中間反抗期」と呼ばれ、早い子では5歳頃から始まり、10歳頃まで続くとされています 1。
これは、2〜3歳頃の「第一次反抗期(イヤイヤ期)」と、思春期真っ只中の「第二次反抗期」の間に位置する、いわば「第二次反抗期への助走期間」のようなものです。
この時期の子どもは、親から精神的に自立しようと、もがき始めている段階です。
そのため、親の言うことに素直に従うのではなく、あえて反発することで「自分」という存在を確立しようとします。
期間には個人差がありますが、子どもの成長に欠かせない大切なステップだと理解しておくと、少し気持ちが楽になるかもしれませんね。
男の子と女の子の態度の違い

中間反抗期の現れ方には、男女で少し違いが見られることがあります。
もちろん個人差が大きいですが、一般的な傾向を知っておくと、お子さんの行動を理解するヒントになります。
| 男の子の特徴 | 女の子の特徴 | |
|---|---|---|
| 表現方法 | 行動や沈黙で示すことが多い 6。 | 言葉や態度で示すことが多い 8。 |
| 具体的な行動 | 物に当たったり、ドアを強く閉めたりする 6。口数が減り、「別に…」と会話を終わらせがち 10。 | 無視、皮肉、冷たい言い方が増える 8。理路整然と口答えをしてくることも 11。 |
| 心理的な背景 | 複雑な感情を言葉で表現するのが苦手、または面倒だと感じている 7。 | 他者からどう見られるかに敏感になり、特に母親に強く反発することで自立しようとする 12。 |
特に女の子の場合、一番身近な同性であるお母さんに対して「自分はママとは違う一人の人間だ」とアピールするために、反発が強くなる傾向があります 。
これは決して母親が嫌いになったわけではなく、むしろ心理的な距離が近いからこそ起こる現象なのです。
口答えや無視をする心理

「宿題やったの?」と聞けば「今やろうと思ってたのに!」と口答え。
「今日の学校どうだった?」と尋ねても無視…。こうした態度は、親としては本当に堪えますよね。
この行動の裏には、いくつかの心理が隠されています。
口答えや無視に隠された子どもの心理
- 自立心の芽生え:「親の言う通りにはなりたくない」「自分で決めたい」という気持ちが強くなり、指示されること自体に反発しています。
- 思考能力の発達:物事を論理的に考えられるようになり、親の言動の矛盾を鋭く指摘したり、屁理屈で対抗したりします 6。これは新しく手に入れた能力を試している証拠でもあります。
- 親への甘えと信頼:実は「こんな態度をとっても見捨てられないはず」という親への深い信頼感の裏返しでもあります 7。外の学校社会で頑張っている分、家では安心して感情を爆発させているのです。
口答えをされたときは、真正面から言い返すのではなく、「そうなんだね」と一度受け止める姿勢を見せることが、こじらせないためのポイントかもしれません。
嘘をつく、物を壊す行動の理由
反抗期がエスカレートして、嘘をついたり、物を壊したりするようになると、親としては「このままで大丈夫だろうか」と深刻に悩んでしまいますよね。
子どもが嘘をつくのは、多くの場合、自分に都合の悪いことから逃れたい、親に叱られたくないという気持ちからです。
この時期はプライドも高くなるため、失敗を認めたくないという心理も働きます。
また、物を壊すという行動は、自分の内側にあるイライラや不満、思い通りにならないもどかしさを、うまく言葉で表現できないために起こります。
特に男の子に多い傾向ですが、溜まったストレスやエネルギーを暴力的な形で発散させてしまっている状態です。
これらの行動は、子ども自身も「やってはいけないこと」とわかっていながら、感情のコントロールが追いつかずにやってしまうケースがほとんど。
行動そのものを厳しく叱るだけでなく、その背景にある子どものストレスや葛藤に目を向けることが大切です。
親への暴力、これって大丈夫?
反抗的な態度が、親への暴力にまで発展してしまった場合、それは非常に深刻なサインです。
物に当たるだけでなく、親を叩いたり蹴ったりする行動がみられるようになったら、それは「中間反抗期」の範疇を超えている可能性も考えなければなりません。
子どもが親に暴力をふるう背景には、
- 自分の感情をコントロールできない強いストレス
- 言葉で伝えられない深い悩みや苦しみ
- 「これくらいやっても許される」という甘えの歪み
などが考えられます。
いかなる理由があっても、暴力は決して許されることではありません。
もしお子さんの暴力が常態化している、エスカレートしている、あるいは親自身が恐怖を感じるような状況であれば、家庭内だけで解決しようとせず、後述する専門機関へ相談することを強く推奨します1。
親が一人で抱え込むことは、状況をさらに悪化させる可能性があります。
子どものためにも、そして親自身のためにも、勇気を出して外部の助けを求めることが重要です。
ひどい5年生の反抗期への正しい接し方
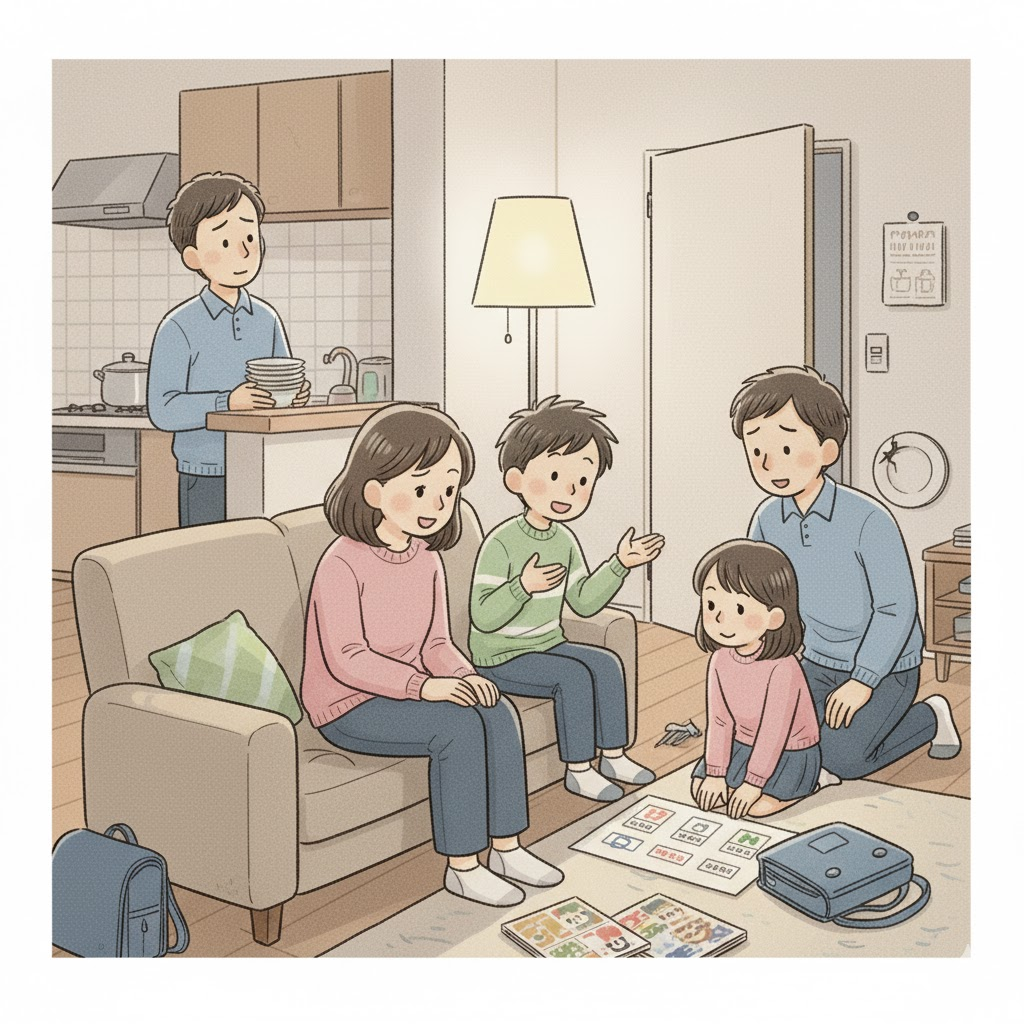
嵐のような反抗期を乗り切るためには、親の対応がカギとなります。
これまでの「管理する親子関係」から、「子どもの自立を見守り、サポートする関係」へとシフトしていく意識が求められます。
ここでは、親子関係を壊さずにこの時期を乗り越えるための具体的な方法を見ていきましょう。
親の対応でやってはいけないこと
良かれと思ってやっていることが、実は火に油を注いでいる…なんてことも。
まずは、反抗期を悪化させがちなNG対応を知っておきましょう。
反抗期の子どもへのNG対応リスト
- 感情的に怒鳴り返す:子どもは恐怖で心を閉ざし、本当に困ったときに相談できなくなります 6。親が感情をコントロールする姿を見せることが大切です。
- 正論で論破する:「正しさ」を振りかざしても、子どもは「気持ちを分かってくれない」と感じ、さらに頑なになるだけです7。
- 他の子や兄弟と比較する:「〇〇ちゃんは偉いのに」という言葉は、子どもの自己肯定感を根底から破壊します 7。
- 人格や友達を否定する:「本当にだらしない子ね」「あの子と遊ぶな」といった言葉は、子どもの世界そのものを否定することになり、信頼を一瞬で失います 6。
- 突き放す・無視する:「勝手にしなさい」という態度は、「見捨てられた」と子どもを深く傷つけ、心の拠り所を奪ってしまいます 7。
- 質問攻めにする:心配のあまり根掘り葉掘り聞くのは、「詮索されている」と感じさせ、子どもをさらにガードさせます 。
これらの対応は、子どもの自立心を傷つけ、親への不信感を募らせるだけです。ついカッとなってしまいそうな時は、一呼吸おいて冷静になることを心がけたいですね。
親が疲れた時の息抜きの方法
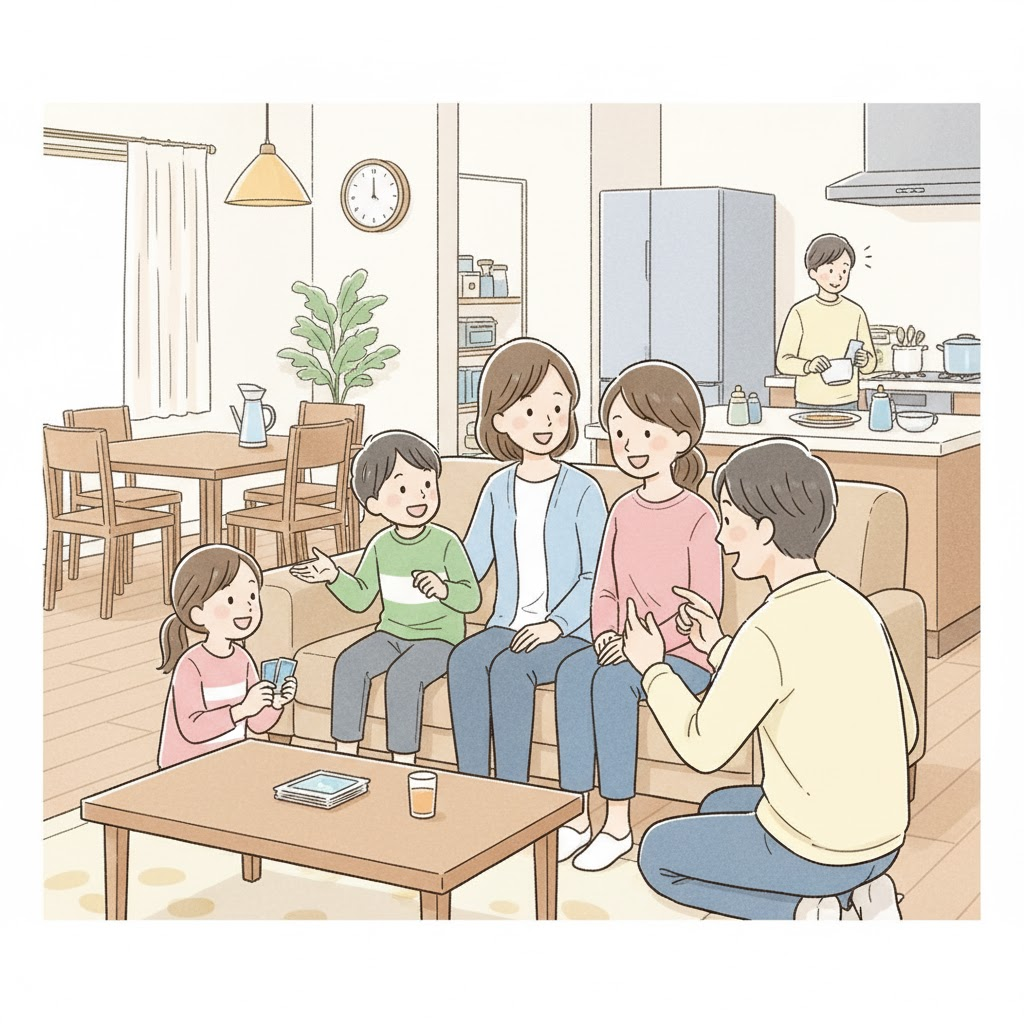
毎日続く反抗的な態度に、親だって疲れてしまいます。親が心身ともに疲れ果てていては、子どもの荒波に寄り添うことなんてできませんよね。
親が笑顔でいることが、子どもにとって一番の安心感に繋がります 19。だからこそ、意識的に息抜きの時間を作ることがとても重要です。
親のための息抜きアイデア
- 物理的に距離を置く:短時間でもいいので、一人でカフェに行ったり、好きな買い物をしたりして、子どものことから離れる時間を作りましょう。
- 誰かに話を聞いてもらう:パートナーや信頼できる友人に、ただただ愚痴を聞いてもらうだけでも心は軽くなります。「うちもそうだよ」と共感してもらえると、一人じゃないんだと思えますよね 。
- 趣味に没頭する:好きなドラマを一気見したり、昔の趣味を再開したり…。子育てとは全く関係ないことに夢中になる時間も大切です。
- 「まあ、いっか」と諦める:完璧な親でいようと頑張りすぎないこと。部屋が多少散らかっていても、宿題をやっていなくても、「まあ、いっか」と良い意味で諦めることも、心を楽にするコツです。
親が自分のご機嫌を自分でとることは、決してわがままではありません。家族みんなが穏やかに過ごすために必要なことなのです。
干渉を嫌がる子への距離の取り方
「ほっといて!」「関係ないでしょ!」…干渉を嫌がる子どもに、どう関わればいいのか悩みますよね。この時期の子どもにとって、親の過干渉は「信頼されていない」「自分の力を信じてもらえない」というメッセージに聞こえてしまいます 。
大切なのは、「管理」から「見守り」へスタンスを変えることです。
例えば、宿題をなかなか始めなくても、「やりなさい!」と何度も言うのではなく、本人が困るまで待ってみる。
もし忘れて先生に叱られたとしても、それは本人が「自分の行動の結果」を学ぶ貴重な経験になります 。
もちろん、すべてを放任するわけではありません。危険なことや、人として許されないことの線引きは明確に伝えつつ、それ以外のことは「あなたを信じているから任せるよ」という姿勢で、少し離れた場所から見守る勇気を持ちましょう。
子どもが助けを求めてきたときには、いつでも手を差し伸べられる準備をしておく。その安心感が、子どもの自立心を健やかに育む土台となります。
専門家への相談を考えるサイン
中間反抗期は成長過程の一部ですが、時には家庭だけでは抱えきれないほど深刻化することもあります。
親が一人で悩み続け、親子関係が修復不可能なほどこじれてしまう前に、専門家の力を借りることは、賢明で愛情深い選択です。
こんなサインが見られたら相談を検討しましょう
- 暴力が常態化している:親や兄弟に日常的に手をあげる、自傷行為が見られる 。
- 学校生活への深刻な支障:長期の不登校や、学校での暴力・いじめなど、問題行動が家庭外にも及んでいる5。
- 心身の不調:持続的な気分の落ち込み、不眠、食欲不振など、うつ病などを疑わせるサインがある。
- 親自身が限界:親が精神的に追い詰められ、不眠や体調不良に陥っている1。
相談先としては、まず身近な「スクールカウンセラー」が挙げられます 。
学校での様子も把握しており、無料で相談に乗ってくれます。
より専門的な対応が必要な場合は、「児童相談所」(全国共通ダイヤル:189)や、「児童精神科・小児科」といった医療機関も選択肢になります 。
これらの情報はあくまで一般的な目安です。お子さんの状態について具体的な診断やアドバイスが必要な場合は、必ず専門の医療機関や相談機関にご相談ください。
嵐を乗り越える家庭のルール作り
「自由にしてほしい!」と叫ぶ反抗期の子どもですが、実は心の奥底では「安心できる枠組み」を求めています。
ルールは子どもを縛り付けるためではなく、無用な衝突を避け、子どもが自分で自分をコントロールする力を育むために存在します。
効果的なルール作りのポイントは3つです。
- ルールは「一緒に」作る
親が一方的に押し付けたルールは、ただの反発の対象になります 28。大切なのは、家族会議などを開いて、子どもの意見も聞きながら一緒に決めること。「なぜこのルールが必要か」を話し合うプロセスが、子どもの納得感に繋がります。
- ルールは「シンプル」に
守るべきルールは、「暴力は絶対にダメ」「挨拶はする」など、家庭にとって本当に譲れないことに1〜3つ程度絞りましょう 7。それ以外は、ある程度子どもの裁量に任せることで、親の負担も軽くなります。
- 「罰」ではなく「結果」を体験させる
ルールを破った時のペナルティも事前に決めておきますが、それは親が与える「罰」ではなく、その行動がもたらす「自然な結果」を本人が引き受ける形が理想です。
例えば、「門限を破ったら、次の外出はなし」ではなく、「門限を破ったら、なぜ遅れたのかを自分で説明し、次の外出許可を自分で交渉する」といった形です。
このプロセスを通じて、子どもは「自由には責任が伴う」という社会の基本原則を学んでいくのです。
ひどい5年生の反抗期は成長の証

ここまで、ひどいと感じる小学5年生の反抗期について、その原因から対処法までお話ししてきました。
今、目の前で繰り広げられる嵐のような日々に、心が折れそうになることもあるかもしれません。
しかし、この嵐は、お子さんが一人の人間として自立するために、どうしても通らなければならない大切な通過儀礼なのです。
反抗的な言葉の裏にある「わかってほしい」という叫びを聞き、管理するのではなく、少し離れた場所から見守る。小さな勝ち負けにこだわるのではなく、長期的な信頼関係を築くことを優先する。
この困難な時期を、親子でなんとか乗り越えたとき、きっとそこには以前とは違う、新しい景色が広がっているはずです。
それは、お互いを一人の人間として尊重し合える、より成熟した親子関係です 。
今まさに渦中にいる親御さん、あなたは一人ではありません。どうかご自身を責めすぎず、時には肩の力を抜いて、この嵐が過ぎ去るのを待ってみてください。その先には、必ず穏やかな日々が待っています。


